『シラス災害―災害に強い鹿児島をめざして―』
岩松 暉 著
第7章 災害に強い鹿児島をめざして
社会現象としての災害|自然とのつきあい方|鹿児島における防災都市づくり
社会現象としての災害
以上、シラス災害のメカニズムと予知予測について述べた。ハザードマップを作り、危険が予想される斜面について防災工事を施せばシラス災害は根絶できるのであろうか。しかし、どんなにテクノパワーを駆使して万全の対策を施しても、崖崩れや洪水を100%防ぐことは不可能に近い。何となれば、それらは太古の昔から繰り返されてきた自然の摂理だからである。山崩れや土石流も侵食現象の一形態に過ぎない。1993年災害でも、シラスだけでなくあらゆる地質のところで崖崩れが発生したことがその普遍性を物語る。前述のように、緑豊かに植生が繁茂し、これに伴って肥沃な土壌が形成される。この土壌が山崩れや土石流によって下流に供給されることにより、平野が形成され、農耕が成り立つ。海岸侵食も防止されるのだ。洪水や氾濫は土砂のもっとも有効な運搬手段である。自然界はこうした微妙な動的バランスを保っているのである。そういう意味では、自然現象としての山崩れ・土石流・洪水などは決してなくならないし、なくなっては困るのである。しかし、それが災害になるか否かという点になると話は別である。無人島で山崩れが起きても単なる地質現象に過ぎない。人命や財貨が失われ、人間社会に損害を与えるとき災害となる。寺田寅彦も地震と震災との峻別を唱え、地震の発生は防げないが震災は人間の努力次第でいかようとも軽減できると主張した。実際、同程度の地震が発生しても発展途上国では104人オーダーの犠牲者が出るが、津波被害を除けばわが国では数10人以下である。耐震工学の進歩とそれを実際の建築に生かすことが出来る経済力のお陰である。1993年の冷害は天明飢饉や「寒サノ夏ハオロオロ歩キ」と賢治が詠った昭和初期の冷害と気象現象としては同規模かそれ以上だったという。天明期には過酷な年貢制度が数万人と言われる餓死者を出した(名君上杉鷹山のいた米沢藩ではほとんど餓死者が出ていない)。昭和初期の冷害では幕末の農業技術の進歩と幕藩体制の崩壊によってさすがに餓死者は出なかったが、まだ地主制度があったため、小作人は娘を花柳界に売り飛ばして口に糊した。1993年の冷害は経済大国ニッポンの円の力で諸外国の米を買いあさって乗り切った。もちろん、餓死者も娘の身売りも出ていない。このように同じような自然現象が発生しても、社会経済情勢が違えば災害として発現する程度が異なるのである。
すなわち、いわゆる自然災害とは単なる自然現象ではなく、自然と社会の交錯するところで発生する社会現象なのである。このことは、防災に関しては自然現象の制御と共に社会的ソフト的対応も重要であることを意味する。なお、天災・人災なる二者択一論がある。天災論は災害を自然現象と混同しており、宿命論やあきらめへ導くし、機械的人災論は自然的要因の軽視につながり、ハード万能主義と結びつきやすい。いずれも真に災害をなくすことにはならない。小出 博が「人災」という造語を提唱した頃はまだ自然現象と自然災害が混同されていた時代で、人為的要因や拡大要因に目を向けさせる積極的意義があったが、現在は行政糾弾といった非常に一面的な使われ方をしており、本質を見誤らせる恐れが強く不毛である。
自然とのつきあい方
自然現象の制御といっても自然と力で全面対決しようとすれば要塞都市のような殺伐としたコンクリートジャングルになってしまう上に、なおかつ自然の力を完全に抑え込むことはできない。明治以来、水害を防ぐために延々と連続堤防を築き、三面張りのコンクリート河川まで構築した。遊水地をなくして堤防に換え上流の氾濫を防ぐ。それが下流の氾濫を招き、下流の連続堤防は天井川を出現させた。近代技術を過信してギリギリまで土地利用し、かえって被害を大きくしてしまう。防災施設が逆に災害要因に転化するのである。それだけではない。コンクリート河川は粘土鉱物による有害物質の吸着を阻害するから、汚染水がそのまま河口に直行し漁業にダメージを与える。砂防ダムは鉄分不足の水を供給し磯焼けを起こすという。自然界はシームレスの織物に例えられる。相互に複雑に絡み合った有機体である。自然の理をわきまえず、近視眼的に征服をもくろむと、とんでもないところでしっぺ返しを食らう。やはり、災害絶滅ではなく災害軽減(災害の無害化)の道を選ぶほうがより賢いやり方であろう。その点、第3章で紹介した洗出のように、祖先の知恵には学ぶべき点が多々ある。信玄堤(霞堤)・輪中・遊水池など典型例である。頻繁な中小氾濫には対処するが、数十年に一度といった例外にはある程度の被害は甘受しようという一病息災の発想である。昔は慢性喘息では死なないと言われてきた。乾布摩擦で体力をつけ、軽微な発作で済ませる対処法である。最近は強い吸入薬でピタッと抑えるため、つい使用頻度が高くなり、心臓に負担をかけて死に至るのである。もちろん、防災工事が無意味だと言っているのではない。既に人家が密集してしまって、生命財産が失われる恐れの強いところには対策を講じなければならない。重症の発作には注射もやむを得ない。しかし、そうした危険なところに住む前に、自然の理をわきまえた賢明な土地利用が必要である。
 写真のように、鹿児島のシラス崖の下には大抵なだらかな坂の部分がある。この坂が終わって平地との境界、道路際の緑地(写真左下)は西郷屋敷跡の公園である。征韓論に破れた西郷隆盛が蟄居していたところという。当時住宅はこの付近が限界で、山際の閑静な住宅だったのだろう。このなだらかな坂の部分こそ崩壊土砂の堆積地形であり、崖崩れ土砂の最大到達距離を示している。自然のままなら崖錐は水が豊富だから、この部分は竹薮か雑木林になっていたであろう。明治以前ここは自然の領域であって、筍採りや薪取りに行くことはあっても、宅地にすることはなかった。祖先はこの部分が危険なことを知っていたのだ。戦後、とくに高度成長期以降、ここに住宅が侵入した。現在のシラス災害はほとんどこの部分で発生している。神様の領分を侵した罰と言えよう。
写真のように、鹿児島のシラス崖の下には大抵なだらかな坂の部分がある。この坂が終わって平地との境界、道路際の緑地(写真左下)は西郷屋敷跡の公園である。征韓論に破れた西郷隆盛が蟄居していたところという。当時住宅はこの付近が限界で、山際の閑静な住宅だったのだろう。このなだらかな坂の部分こそ崩壊土砂の堆積地形であり、崖崩れ土砂の最大到達距離を示している。自然のままなら崖錐は水が豊富だから、この部分は竹薮か雑木林になっていたであろう。明治以前ここは自然の領域であって、筍採りや薪取りに行くことはあっても、宅地にすることはなかった。祖先はこの部分が危険なことを知っていたのだ。戦後、とくに高度成長期以降、ここに住宅が侵入した。現在のシラス災害はほとんどこの部分で発生している。神様の領分を侵した罰と言えよう。本家分家の理論(?)なるものがある。確か天草災害の時言い出された。被災したのは圧倒的に分家が多かったという。古くからある本家は適者として生存してきたのに、新しく作った分家は当面の利便性だけを考慮して立地していたからである。これからの都市計画は利便性・効率性第一主義ではなく、自然の論理(地質学の原理)を踏まえて、環境とも調和をはかりながら行っていかなければならない。真っ白いキャンバスの上に自由に絵を描くセンスでは困るのである。キャンバスの下、地面の下に岩石や地層があることを忘れてはならない。
鹿児島における防災都市づくり
つくば研究学園都市のように全く新しいところに立地するのなら理想的な都市計画も可能だろうが、既存都市の安全性を高めるためにはどうしたらよいのであろうか。鹿児島市の場合、もともと平場が少ないから、高度成長期以来流入人口を吸収するために、山を削り谷を埋め立てて団地を造成してきた。以前なら住まなかった危険地まで進出したために災害が激発するようになったのだ。そろそろ人口膨張は抑制すべきではないだろうか。しかし、いくら地方定住圏構想を打ち上げても、農業で生計が立てられない限り、また教育・文化・医療等の都会偏在が解消しない限り、人口集積効果を求めて集まってくるのは避けられない。これは政治の根本に関わることで、防災云々以前の問題である。どうしても60万都市を目指すのなら、周辺の町々を衛星都市にして平坦地に団地を造成するしかないであろう。ただし、事前の防災アセスメント実施が前提である。また、モノレール・地下鉄等公共交通機関を抜本的に整備して市内へのアクセスを容易にし、マイカー乗り入れを規制することが必要であろう。沿岸部を埋め立て高層マンション群を建設することは、地震時の液状化災害などを考えると避けたほうがよい。もちろん、丘陵部の切り盛りはもう限界に近い。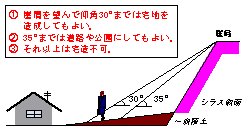 がけ崩れに対しては、「がけ地近接等危険住宅移転事業」の補助率をアップするなどして移転を促進することが望ましい。現在の鹿児島県宅地造成基準では崖肩を望んで仰角30゜以上のところは宅造禁止である(左図)。1976年災害の後制定された。1986年災害直後見直しが行われた(私が座長)が、被災家屋のほとんどがこの30゜ライン内に入っていた。つまりこのラインよりも崖に近づかなければ崖崩れ災害はほとんど発生しないと言ってよい。諸般の事情で住家が存在するところは法面工事をすることもやむを得ない。
がけ崩れに対しては、「がけ地近接等危険住宅移転事業」の補助率をアップするなどして移転を促進することが望ましい。現在の鹿児島県宅地造成基準では崖肩を望んで仰角30゜以上のところは宅造禁止である(左図)。1976年災害の後制定された。1986年災害直後見直しが行われた(私が座長)が、被災家屋のほとんどがこの30゜ライン内に入っていた。つまりこのラインよりも崖に近づかなければ崖崩れ災害はほとんど発生しないと言ってよい。諸般の事情で住家が存在するところは法面工事をすることもやむを得ない。鹿児島はシラス災害以外にもいろいろな災害に見舞われる。防災都市づくりということになると、こうした災害にも触れざるを得ない。以下、個別の災害ごとに論じてみたい。
土石流に対しては、危険渓流の出口付近は避けたほうがよい。土石流は現在の河道と無関係に直進することが多く、旧河道をなぞることもある。こうした箇所は移転するに越したことはない。国道10号線沿いは姶良カルデラ壁に当たっている。「侵食カルデラ」なる術語の存在が示しているように、カルデラ壁は本来侵食作用が活発なところである。地形図上でも過去の崩壊地形が数多く読み取れる。崖崩れや土石流が頻発するのが当然の自然の姿なのである。ここの国道や鉄道は海に張り出すかトンネルで避けるのがよいと思われる。山椒太夫で有名な新潟県の親不知子不知の険では橋梁で通過している。もちろん、カルデラ壁に集落を立地するのは好ましくない。砂防ダムで土石流が止められた例は多いが、カルデラ壁では繰り返し発生するから、あまり過信しないほうがよい。
水害に関しては、水源地での植林を含む総合治水によってピーク時流量を減らすと共に、河川改修によって速やかに排出することなどが考えられる。しかし、上流部の氾濫を防ぐために改修を行えば、当然下流に悪影響を与える。古来、水害では上流と下流で利害が対立し、川騒動がしばしばあった。なかなか両立は難しい。遊水池の復活も過密都市では住家の移転などの問題があってなかなか困難である。数10年確率の洪水には安全なようにハード的対策をとることにして、100年確率以上の大災害に対しては保険で対処するなどの方法が考えられる。昔の水屋にならってゲタ履き住宅を作り1階をガレージにしておくとか、床上浸水はなるべく防ぎ広範囲の床下浸水は甘受するなどのやり方もある。遊水機能の重視である。
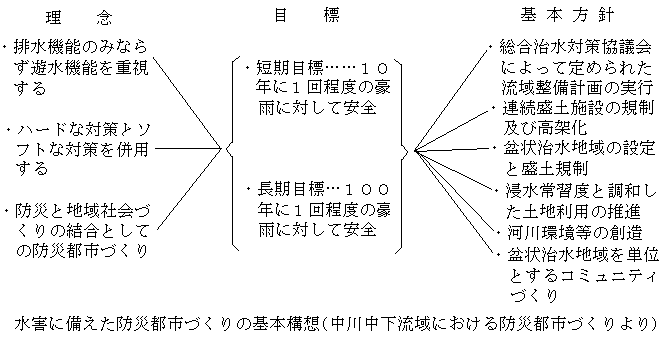 都市型災害の場合には、ライフライン災害の対処法も考えておく必要がある。1993年の災害では、道路と鉄道が寸断されたため、鹿児島市は陸の孤島と化した。もともと島津公は敵が攻め難い天険の地に城下町を構えたのだから当然である。従来、国道10号はしばしば交通が途絶したが、九州自動車道があるために空港方面との連絡は保たれていた。今回初めてこの高速道路が不通になったが、さすがに高規格道路であるから公団の敷地内に起因して発生した災害はほとんどなく、敷地外からの流入土砂によって不通になったのである。国道10号線は前述のようにカルデラ壁にあって不安定だから、この高速道路は鹿児島市にとって生命線とも言える道路である。どんな豪雨でもここだけは守れるよう、沿線周縁部の砂防に重点投資をする必要があると思う。8・6災害でもあった断水・停電・電話不通などの対策も重要である。これからはますますコンピュータ社会になるから、コンピュータネットの保持も忘れてはならない。
都市型災害の場合には、ライフライン災害の対処法も考えておく必要がある。1993年の災害では、道路と鉄道が寸断されたため、鹿児島市は陸の孤島と化した。もともと島津公は敵が攻め難い天険の地に城下町を構えたのだから当然である。従来、国道10号はしばしば交通が途絶したが、九州自動車道があるために空港方面との連絡は保たれていた。今回初めてこの高速道路が不通になったが、さすがに高規格道路であるから公団の敷地内に起因して発生した災害はほとんどなく、敷地外からの流入土砂によって不通になったのである。国道10号線は前述のようにカルデラ壁にあって不安定だから、この高速道路は鹿児島市にとって生命線とも言える道路である。どんな豪雨でもここだけは守れるよう、沿線周縁部の砂防に重点投資をする必要があると思う。8・6災害でもあった断水・停電・電話不通などの対策も重要である。これからはますますコンピュータ社会になるから、コンピュータネットの保持も忘れてはならない。鹿児島は地震の少ないところだが、桜島が大正噴火級の大規模噴火をしたときには震度6クラスの地震に見舞われる恐れがある。大正噴火の際も島内では死者はほとんど出なかったのに、本土側で地震による家屋倒壊や崖崩れが発生して多数の犠牲者が出た。液状化を示唆する記録もある。当時の水田地帯は今や人口密集地であり、シラスの水搬工法による埋立地も多い。北海道南西部地震では火山性堆積物の液状化が話題を呼んだが、鹿児島の沖積平野はまさに二次シラスから出来ている。液状化災害に対する備えも忘れてはならない。阪神大震災では「震災の帯」が問題になった。都市地盤図を整備して、鹿児島における「震災の帯」がどこにあるのか事前に明らかにし、その地域については特別耐震性を強化しておかなければならない。また、建築基準法による規制が他県に比して緩いことから、耐震上問題のある建物も多い。宮城県沖地震で学童が多数下敷きとなって問題となった無鉄筋ブロック塀も多数ある。桜島から避難してきた人達が地理不案内な本土で地震の犠牲になるようなことが起きかねない。地震は決してひと事ではないのである。
火山災害を都市づくりの観点からみるのは難しい。必ず山頂噴火をする火山ならともかく、桜島は山腹噴火もあってどこから噴くか数十年も前から特定できないから、ハード的な対策を立てようがない。磐梯山のような山体崩壊があれば壊滅的で、これに対処することは不可能である。火山山麓に住むこと自体が問題だということになってしまう。やはり避難などソフト的に対応するしかないであろう。幸い「理論ヲ信頼セズ」と恨まれた往時と違って、火山学も進歩したし観測網も充実している。噴火の時期や噴火口の位置等の直前予知は確実に出来るであろうから、事前の対処は可能である。
本ページ先頭|社会現象としての災害|自然とのつきあい方|鹿児島における防災都市づくり
連絡先:iwamatsu@sci.kagoshima-u.ac.jp 更新日:1996年10月13日