『シラス災害―災害に強い鹿児島をめざして―』
岩松 暉 著
第6章 シラス災害の予知予測
電気探査によるシラス災害予知|実効雨量|逓減係数の決め方|崩壊予測|予知システム
電気探査によるシラス災害予知
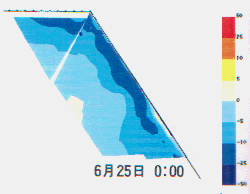 しかし、80mmの雨が降ったら必ずがけ崩れが起きる訳ではない。その前に雨がずっと降り続いていて(先行降雨という)、地面がたっぷりと水を吸い込んでいる場合には、もっと少ない雨量でもがけ崩れの引き金になるし、前日まで乾燥していた場合には、相当の豪雨が降ってもがけ崩れは発生しない。つまり地面の湿り具合が決定的に影響するのである。地面の湿り具合の変化を調べる方法がないものであろうか。中性子水分計のような直接含水量を測定する機器もあるが、高価で貧乏大学にはない。それにあまり深いところまで測定できない。電気探査で比抵抗を測定し、それで代用することにした。水を含むと電気が通りやすくなり、比抵抗値は下がるし、晴天が続いて乾燥してくると、比抵抗値は上がる。間接的ではあるが、地面の湿り具合の指標となる。(株)建設技術研究所から自動電気探査装置をお借りして共同研究することにした。6時間ごと(降雨時には3時間ごと)に自動的に電気を流して測定できる装置である。これを鹿児島空港のある十三塚原台地のシラス斜面に設置した。左図は測定開始日(晴天)を基準値とした変化率Cvを示している。青いところは湿ってきたところ(比抵抗値低下)で、明るい色のところは乾燥してきたところ(比抵抗値増大)である。
しかし、80mmの雨が降ったら必ずがけ崩れが起きる訳ではない。その前に雨がずっと降り続いていて(先行降雨という)、地面がたっぷりと水を吸い込んでいる場合には、もっと少ない雨量でもがけ崩れの引き金になるし、前日まで乾燥していた場合には、相当の豪雨が降ってもがけ崩れは発生しない。つまり地面の湿り具合が決定的に影響するのである。地面の湿り具合の変化を調べる方法がないものであろうか。中性子水分計のような直接含水量を測定する機器もあるが、高価で貧乏大学にはない。それにあまり深いところまで測定できない。電気探査で比抵抗を測定し、それで代用することにした。水を含むと電気が通りやすくなり、比抵抗値は下がるし、晴天が続いて乾燥してくると、比抵抗値は上がる。間接的ではあるが、地面の湿り具合の指標となる。(株)建設技術研究所から自動電気探査装置をお借りして共同研究することにした。6時間ごと(降雨時には3時間ごと)に自動的に電気を流して測定できる装置である。これを鹿児島空港のある十三塚原台地のシラス斜面に設置した。左図は測定開始日(晴天)を基準値とした変化率Cvを示している。青いところは湿ってきたところ(比抵抗値低下)で、明るい色のところは乾燥してきたところ(比抵抗値増大)である。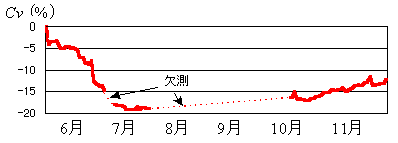 これはある測定点の比抵抗値の変化率Cvの経時変化を示している。梅雨の6~7月にどんどん湿ってきて、夏から秋にかけて少しずつ乾燥してきたことがわかる。湿るのは速いけれど、一旦湿ると乾くのにはずいぶん時間がかかることを意味している。つまり先行降雨の影響が大きいことを示している。
これはある測定点の比抵抗値の変化率Cvの経時変化を示している。梅雨の6~7月にどんどん湿ってきて、夏から秋にかけて少しずつ乾燥してきたことがわかる。湿るのは速いけれど、一旦湿ると乾くのにはずいぶん時間がかかることを意味している。つまり先行降雨の影響が大きいことを示している。
実効雨量
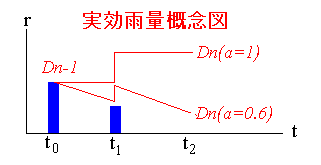 実効雨量という考え方がある。前日までに降った雨の何%かがまだ影響を及ぼしているとして勘定に入れようという訳である。式は次のように与えられる。
実効雨量という考え方がある。前日までに降った雨の何%かがまだ影響を及ぼしているとして勘定に入れようという訳である。式は次のように与えられる。Dn=an-1r1+an-2r2+....+a1rn-1+rn
Dnは降雨開始からn番目の時刻の実効雨量、rnはn番目の時刻の雨量、aは逓減係数(0<a≦1)
問題はこの逓減係数a、つまり前の雨がどの程度後まで影響を与えるかの係数をどの程度と見積もるかが鍵になる。a=1なら累加雨量と同じで、降った雨は後まで100%影響を与えるということを意味する。a=0なら以前の雨は全く影響を与えず、その時の雨量強度だけが問題だという訳である。今までこの逓減係数は適当な値を仮定してやっていた。山勘方式である。また、降り始めをどこからとするかも問題である。1時間以上降雨の中断があるとリセットされてゼロから累加雨量は計算されるのが普通だが、その前に大雨があれば当然地面は水を多く含んでいるはずである。カラカラ天気の後初めて降った場合とは同列に扱えない。もう少しましな決め方はないものであろうか。
逓減係数の決め方
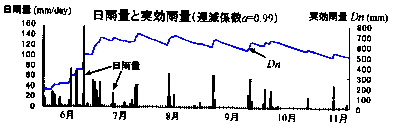 これはA=0.99とした時の、上と同じ期間の実効雨量Dnのグラフである。上のカーブと大変よく似ている。上下ひっくり返したらぴったり一致するではないか。両者のカーブが一番よく一致する時のaの値で実効雨量を決めれば、従来の山勘方式に比べてずっとリーズナブルな実効雨量が求められるのではないだろうか。こうした観測をあちこちの斜面で実施して、それぞれの地域ないし斜面ごとに固有のaの値を求めることができる。
これはA=0.99とした時の、上と同じ期間の実効雨量Dnのグラフである。上のカーブと大変よく似ている。上下ひっくり返したらぴったり一致するではないか。両者のカーブが一番よく一致する時のaの値で実効雨量を決めれば、従来の山勘方式に比べてずっとリーズナブルな実効雨量が求められるのではないだろうか。こうした観測をあちこちの斜面で実施して、それぞれの地域ないし斜面ごとに固有のaの値を求めることができる。また、このことは、実効雨量が地面の下の状況を判断するのになかなか有効な考え方だということも意味する。
なお、もっとも相関の良い時のaの値を各測定点についてすべて計算してやると、斜面表層ほど小さく、深部ほど1に近づく。表面から乾燥が進み、深部は一度湿るとなかなか乾かない訳だから、当然のことである。
崩壊予測
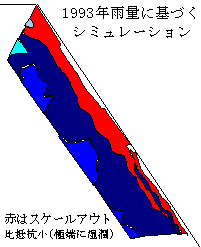 CvとDnとの間に規則的な関係があることがわかったから、降雨の観測だけで比抵抗値の変化、つまり地面の湿り具合の変化を予測できる。左図は1993年の鹿児島豪雨災害時の雨量データから、この斜面でのaの値を用いて実効雨量を計算し、さらに比抵抗値を推定したものである。上の図とはずいぶん違って著しく湿っていたことがわかる。この斜面は当時崩壊しなかったが、周辺の斜面はあちこち崩れた。恐らくこの斜面も崩壊寸前だったはずである。比抵抗値がこの程度まで低下したら、危険と判断して避難などの対策を取るべきであろう。
CvとDnとの間に規則的な関係があることがわかったから、降雨の観測だけで比抵抗値の変化、つまり地面の湿り具合の変化を予測できる。左図は1993年の鹿児島豪雨災害時の雨量データから、この斜面でのaの値を用いて実効雨量を計算し、さらに比抵抗値を推定したものである。上の図とはずいぶん違って著しく湿っていたことがわかる。この斜面は当時崩壊しなかったが、周辺の斜面はあちこち崩れた。恐らくこの斜面も崩壊寸前だったはずである。比抵抗値がこの程度まで低下したら、危険と判断して避難などの対策を取るべきであろう。
予知システム
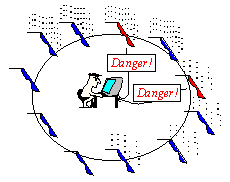 まとめてみる。①まず、その地域の代表的な斜面で上記のような長期電探と降雨の観測を実施し、実効雨量逓減係数aの値を決める。②後は雨量計だけを残し、降雨データを県庁などの防災機関にオンラインで集中する(電探は金と手間暇がかかるから、aが求まった段階で中止し、他の場所に移動して次の観測を行う)。③防災機関では降雨データとaの値から実効雨量および比抵抗の変化を常時計算で出しておく。④比抵抗が臨界値に達したら警戒態勢に入り、消防の出動や避難命令など適切な処置を取ればよい。
こうした段取りで、シラス災害予知警報システムができるのではないだろうか。もちろん、1993年が臨界値だったというのは推定に過ぎないから、現在の観測点は実際に崩壊するまでそのまま観測を続け、真の臨界値を求めたいものである。しかし、いつまでも民間会社のご好意に甘える訳にもいかない。できれば行政でこの先はやってもらいたいものだ。
まとめてみる。①まず、その地域の代表的な斜面で上記のような長期電探と降雨の観測を実施し、実効雨量逓減係数aの値を決める。②後は雨量計だけを残し、降雨データを県庁などの防災機関にオンラインで集中する(電探は金と手間暇がかかるから、aが求まった段階で中止し、他の場所に移動して次の観測を行う)。③防災機関では降雨データとaの値から実効雨量および比抵抗の変化を常時計算で出しておく。④比抵抗が臨界値に達したら警戒態勢に入り、消防の出動や避難命令など適切な処置を取ればよい。
こうした段取りで、シラス災害予知警報システムができるのではないだろうか。もちろん、1993年が臨界値だったというのは推定に過ぎないから、現在の観測点は実際に崩壊するまでそのまま観測を続け、真の臨界値を求めたいものである。しかし、いつまでも民間会社のご好意に甘える訳にもいかない。できれば行政でこの先はやってもらいたいものだ。
本ページ先頭|電気探査によるシラス災害予知|実効雨量|逓減係数の決め方|崩壊予測|予知システム
連絡先:iwamatsu@sci.kagoshima-u.ac.jp 更新日:1996年10月13日