『シラス災害―災害に強い鹿児島をめざして―』
岩松 暉 著
第6章 シラス災害の予知予測
災害の予知|シラス災害の空間的予知|シラス災害の時間的予知
災害の予知
災害の予知というと東海地震予知のことがすぐ思い浮かぶ。これがあまりにも有名になったため、予知=時間的予知と受け取られるようになった。何時起きるかも重要であるが、どこが危ないかも重要である。つまり空間的予知である。何時起きるかが正確にわかれば避難誘導や交通規制・消防の出動など、さまざまな直前対策がとれる。しかし、どこが危ないかがわかれば、事前の防災工事も行え、災害に強い町づくりが出来る。わが町の「震災の帯」がどこにあるかがわかれば、その一帯の建物を耐震耐火建築にするなど重点投資を行えばよい。直前対策や応急対策よりももっと本質的な防災対策に資することが出来る。しかし、抜本的な防災国土づくりには多額の費用がかかる。貧弱な国土保全投資を覆い隠し、本腰で災害対策をやっているかのごとく国民を錯覚させるために、地震学者にわずかな研究費を与えて誤魔化しているとしか思えない。地震予知イチジクの葉っぱ論は言い過ぎであるが、もっと空間的予知の重要性を認識して欲しいと思う。この度の阪神大震災で、ようやくハザードマップ作成や都市地盤図整備などの動きが出てきたことは喜ばしい。6,000人の犠牲者が出て、ようやく腰を上げるようでは遅すぎるが。
シラス災害の空間的予知
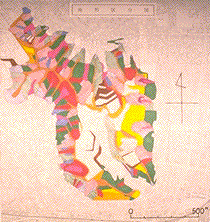
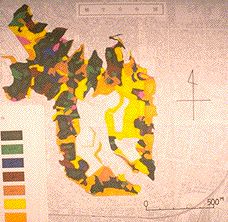
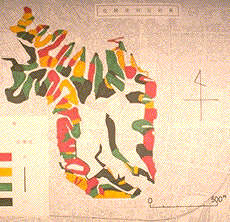 鹿児島にはシラスがけが何10万個所もある。どのがけが危ないか、片っ端から地質調査するのは確かに大変である。そこで、先ず外から概観しただけでわかる地形と植生に注目してみよう。前章で述べたことから、水の集中しやすい谷型斜面で、壮齢広葉樹林のところが要注意である。多変量解析の手法を用いて、要注意個所の抽出を試みる。1986災害で崩れたところが一番危険なAランクと出るよう、カテゴリとアイテムを定めるのである。上図はあるモデル地域について地形(左図)と植生(中央)から危険度判定を試みた結果(右図)である(もちろん、実際はもっと多くの要素を考慮した)。1986災害で崩れなかったところで、Aランクと出たところが、今後もっとも崩れる可能性の高い要注意箇所である。
鹿児島にはシラスがけが何10万個所もある。どのがけが危ないか、片っ端から地質調査するのは確かに大変である。そこで、先ず外から概観しただけでわかる地形と植生に注目してみよう。前章で述べたことから、水の集中しやすい谷型斜面で、壮齢広葉樹林のところが要注意である。多変量解析の手法を用いて、要注意個所の抽出を試みる。1986災害で崩れたところが一番危険なAランクと出るよう、カテゴリとアイテムを定めるのである。上図はあるモデル地域について地形(左図)と植生(中央)から危険度判定を試みた結果(右図)である(もちろん、実際はもっと多くの要素を考慮した)。1986災害で崩れなかったところで、Aランクと出たところが、今後もっとも崩れる可能性の高い要注意箇所である。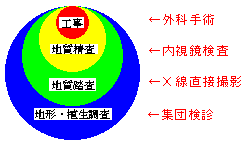 しかし、人手のない大学人が県内全域の調査に当たるのは不可能に近い。非専門家の行政マンでも調査判定が行えるよう、ノートパソコンに組み込んだエキスパートシステムも開発した。名付けてAI診断という(人工知能Artificial intelligenceのことで私のイニシャルでもある)。これを行政マンに持たせて人海作戦をやればよい。成人病検診になぞらえれば、X線間接撮影による集団検診である。こうして抽出した要注意個所について、土壌の厚さやボラの有無・古地形などを地質調査によって調べる。X線直接撮影に当たる。さらに要精密検査個所については胃カメラを飲ませる。物理探査やボーリングなど地質精査である。この中から更に要工事個所(外科手術)や、住宅の要移転個所を抽出すればよい。成人病検診だって何10万人を対象としているのだから、シラスがけだって実行可能なのではないだろうか。
しかし、人手のない大学人が県内全域の調査に当たるのは不可能に近い。非専門家の行政マンでも調査判定が行えるよう、ノートパソコンに組み込んだエキスパートシステムも開発した。名付けてAI診断という(人工知能Artificial intelligenceのことで私のイニシャルでもある)。これを行政マンに持たせて人海作戦をやればよい。成人病検診になぞらえれば、X線間接撮影による集団検診である。こうして抽出した要注意個所について、土壌の厚さやボラの有無・古地形などを地質調査によって調べる。X線直接撮影に当たる。さらに要精密検査個所については胃カメラを飲ませる。物理探査やボーリングなど地質精査である。この中から更に要工事個所(外科手術)や、住宅の要移転個所を抽出すればよい。成人病検診だって何10万人を対象としているのだから、シラスがけだって実行可能なのではないだろうか。
シラス災害の時間的予知
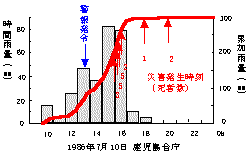 もちろん、時間的予知も重要である。長期的時間予知としては、植物遷移の項で述べたように、樹齢80~100年程度の広葉樹林で、表土の層厚が数10cmのところがそろそろ危ないところである。豪雨の最中の何時避難すべきかといった短期的時間予知には、やはり降雨量が使われる。左図に1986年災害時の降雨状況を示す。赤矢印が人的被害の出た時刻で(数字は死者数)、時間雨量が80mm、降り始めからの累加雨量が200mmになった頃からがけ崩れが発生し始めている。それ故、安全を見込めば、時間雨量50mm、累加雨量150mm程度になったら避難したほうがよい。しかし、気象台のロボット雨量計の配置網は、豪雨をもたらす雨雲(豪雨セル)のスケールに比して粗すぎる。1986年災害の時、アメダスの雨量が1mmだったことが象徴している。したがって、消防署など役所からの避難命令を待っていたのでは遅すぎる。災害は自分の命は自分で守るのが鉄則である。大雨になってきたら、コップ(なるべくならラッパ型ではなく円筒型のもの)を屋外に出すよう心がけよう。2時間で一杯になるようなひどい降り方ならほぼ時間雨量50mmである。安全なところに逃げ出したほうがよい。避難所は地区ごとに指定されているはずだから、自分の家の近くの避難場所を覚えておこう。こうしたコップを外に出すこころがけは、災害に対して常日頃から関心を持つことにつながる。
もちろん、時間的予知も重要である。長期的時間予知としては、植物遷移の項で述べたように、樹齢80~100年程度の広葉樹林で、表土の層厚が数10cmのところがそろそろ危ないところである。豪雨の最中の何時避難すべきかといった短期的時間予知には、やはり降雨量が使われる。左図に1986年災害時の降雨状況を示す。赤矢印が人的被害の出た時刻で(数字は死者数)、時間雨量が80mm、降り始めからの累加雨量が200mmになった頃からがけ崩れが発生し始めている。それ故、安全を見込めば、時間雨量50mm、累加雨量150mm程度になったら避難したほうがよい。しかし、気象台のロボット雨量計の配置網は、豪雨をもたらす雨雲(豪雨セル)のスケールに比して粗すぎる。1986年災害の時、アメダスの雨量が1mmだったことが象徴している。したがって、消防署など役所からの避難命令を待っていたのでは遅すぎる。災害は自分の命は自分で守るのが鉄則である。大雨になってきたら、コップ(なるべくならラッパ型ではなく円筒型のもの)を屋外に出すよう心がけよう。2時間で一杯になるようなひどい降り方ならほぼ時間雨量50mmである。安全なところに逃げ出したほうがよい。避難所は地区ごとに指定されているはずだから、自分の家の近くの避難場所を覚えておこう。こうしたコップを外に出すこころがけは、災害に対して常日頃から関心を持つことにつながる。
本ページ先頭|災害の予知|シラス災害の空間的予知|シラス災害の時間的予知
連絡先:iwamatsu@sci.kagoshima-u.ac.jp 更新日:1996年10月13日