『シラス災害―災害に強い鹿児島をめざして―』
岩松 暉 著
第2章 シラスとは
ボラ(降下軽石)|薩摩降下軽石|ボラの特徴
ボラ(降下軽石)
 次に、シラスとよく混同されるのにボラがある。前述の竹迫団地の悲劇はこの混同にあった。やはり鹿児島地方の方言に由来する。厄介者、困り者の意という。園芸に使われる鹿沼土のような径1~2cmの黄褐色軽石を指す。地質学的には降下軽石のことである。火砕流と違って流れたものではなく、一旦空高く噴き上げられた軽石が空中を飛翔して落下したものをいう。霧島ボラ、桜島ボラなどのように噴出源を冠したり、大正ボラ、安永ボラのように噴出時期を冠したりして使われる。ちなみに鹿沼土は赤城火山起源の降下軽石である。赤城山は群馬県にあるが鹿沼市はその真西栃木県にある。西風に乗って飛んできたものであろう。やはり、土質工学会では平仮名書きにしている。
次に、シラスとよく混同されるのにボラがある。前述の竹迫団地の悲劇はこの混同にあった。やはり鹿児島地方の方言に由来する。厄介者、困り者の意という。園芸に使われる鹿沼土のような径1~2cmの黄褐色軽石を指す。地質学的には降下軽石のことである。火砕流と違って流れたものではなく、一旦空高く噴き上げられた軽石が空中を飛翔して落下したものをいう。霧島ボラ、桜島ボラなどのように噴出源を冠したり、大正ボラ、安永ボラのように噴出時期を冠したりして使われる。ちなみに鹿沼土は赤城火山起源の降下軽石である。赤城山は群馬県にあるが鹿沼市はその真西栃木県にある。西風に乗って飛んできたものであろう。やはり、土質工学会では平仮名書きにしている。薩摩降下軽石
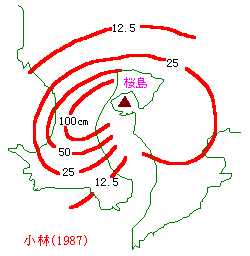 鹿児島地方に広く分布しているのは大隅半島の大隅降下軽石と、薩摩半島の薩摩降下軽石である。前者についてはすでに述べた。シラスを噴く前の初期噴火の産物だから、一般にシラスの下面に存在する。もちろん、空から降ったものであるから、高隈山のような基盤岩をも直接覆っている。
鹿児島地方に広く分布しているのは大隅半島の大隅降下軽石と、薩摩半島の薩摩降下軽石である。前者についてはすでに述べた。シラスを噴く前の初期噴火の産物だから、一般にシラスの下面に存在する。もちろん、空から降ったものであるから、高隈山のような基盤岩をも直接覆っている。これに対して薩摩降下軽石はもっと新しい。入戸火砕流を噴出した後の後カルデラ火山として桜島火山が約1.1万年前に誕生した。阿蘇中岳のような中央火口丘としてではなく、姶良カルデラの端に生まれた行儀の悪い鬼っ子である。
この桜島の誕生に伴う初期噴火、いわば産声として大量の軽石を噴出した。東南の風に乗り、主として薩摩半島に降り積もったので、薩摩降下軽石という。鹿児島市内で約1mの厚さがある。
ボラの特徴
 シラスと違って流れてきたものではなく、空を飛んできて積もったものだから、その特徴がある。第一の特徴は淘汰がよい(粒径が揃っている)ことである。重いものは早く落ちるし、軽いものは遠くまで飛んで行く。したがって、同じ場所には同じような大きさのものが堆積する。シラスのように細かな火山灰がセメントの役割を果たしていないので、空隙が極めて大きい。畑にしようと思って、いくら水や肥料を撒いても、スーッとしみ込んで肥料保ちが悪い。全く不毛である。やむなくボラを地表から排除して畑にした。ブルドーザーのなかった時代、ボラ抜きとかボラ起こしと呼ばれる過酷な労働を農民に強いた。厄介者と名付けられた所以である。
シラスと違って流れてきたものではなく、空を飛んできて積もったものだから、その特徴がある。第一の特徴は淘汰がよい(粒径が揃っている)ことである。重いものは早く落ちるし、軽いものは遠くまで飛んで行く。したがって、同じ場所には同じような大きさのものが堆積する。シラスのように細かな火山灰がセメントの役割を果たしていないので、空隙が極めて大きい。畑にしようと思って、いくら水や肥料を撒いても、スーッとしみ込んで肥料保ちが悪い。全く不毛である。やむなくボラを地表から排除して畑にした。ブルドーザーのなかった時代、ボラ抜きとかボラ起こしと呼ばれる過酷な労働を農民に強いた。厄介者と名付けられた所以である。したがって、極めて透水性がよいから、地層としては透水層の役割を果たすことが多い。これが第二の特徴である。地質時代を通じて常に地下水の通路となっていたので、粘土化が進んで脱色され、指でもつぶれるくらいの柔らかな白色軽石になっていることもある。
第三の特徴は地形に平行に積もっているということである。空から降り注いだ訳だから、当然野にも山にも降り積もる。30度から40度以下の緩い斜面なら、斜面に平行に堆積している。これが後述のボラすべりの原因となる。
本ページ先頭|ボラ(降下軽石)|薩摩降下軽石|ボラの特徴
連絡先:iwamatsu@sci.kagoshima-u.ac.jp 更新日:1996年10月13日