『シラス災害―災害に強い鹿児島をめざして―』
岩松 暉 著
第2章 シラスとは
従来シラスと称されてきたもの|「シラス」か「しらす」か|火砕流|入戸火砕流を噴出した巨大噴火|シラスの特徴
 シラスとはもともと白色砂質堆積物を指す鹿児島地方の方言に由来する。鹿児島では正月を迎えるに当たって庭先にシラスを撒いて清める風習があった。正月どん迎え(しょがっどんむけ)という(写真:南日本新聞による)。奉行所の白州も同語源かも知れない。いずれにせよ今では地形・地質・土木の世界で使われており、地学辞典や学術用語集に採用されている。Tsunamiほどではないがローマ字でそのまま世界に通用するという。少なくとも土木関係の英文論文で見たことがある。
シラスとはもともと白色砂質堆積物を指す鹿児島地方の方言に由来する。鹿児島では正月を迎えるに当たって庭先にシラスを撒いて清める風習があった。正月どん迎え(しょがっどんむけ)という(写真:南日本新聞による)。奉行所の白州も同語源かも知れない。いずれにせよ今では地形・地質・土木の世界で使われており、地学辞典や学術用語集に採用されている。Tsunamiほどではないがローマ字でそのまま世界に通用するという。少なくとも土木関係の英文論文で見たことがある。従来シラスと称されてきたもの
しかし、学術用語として厳密に定義されたものでないから、さまざまな使われ方をしており、混乱している。後述するような火砕流堆積物の非溶結部、その二次的堆積物(いわゆる二次シラス)、第四紀層の白色砂質堆積物、降下軽石(いわゆるボラ)など、軽石質ならば何でもシラスと呼ばれてきた。そのため、専門家同士の会話でも、それぞれ別なイメージで受け取って、誤解が生じたりすることがまま起こる。 地質屋は名称にこだわって、何かと専門語をたくさん作り出す悪癖がある。しかし、成因が異なれば存在する場所も異なり、災害に対する意義も異なる(第3章参照)。ここは、やはり厳密な使い方をすべきであろう。これに関して私には苦い経験がある。1976年の災害時、土木の方たちが降下軽石(ボラ)を水成シラスと呼んでおられるのを知って困ったことだとは思ったが、転勤してきたばかりの新参者でもあり、シラスについてそれほど詳しい訳ではなかったから、あまり声を大にして訂正しなかった。しかし、翌年鹿児島市竹迫団地の造成工事でボラすべり災害が発生したのである。シラスは垂直に切っても比較的安全だから垂直に切っていったが、ボラに突入してもそのまま垂直に切り進んでいった。恐らくどちらも軽石質で同じくシラスと呼ばれていたため、工法を変えようとは思いもしなかったのであろう。その結果、パートのおばさんが3人亡くなってしまった(写真)。もっと土木関係者に地質の知識を普及啓蒙しておくべきだったと後悔したことだった。
地質屋は名称にこだわって、何かと専門語をたくさん作り出す悪癖がある。しかし、成因が異なれば存在する場所も異なり、災害に対する意義も異なる(第3章参照)。ここは、やはり厳密な使い方をすべきであろう。これに関して私には苦い経験がある。1976年の災害時、土木の方たちが降下軽石(ボラ)を水成シラスと呼んでおられるのを知って困ったことだとは思ったが、転勤してきたばかりの新参者でもあり、シラスについてそれほど詳しい訳ではなかったから、あまり声を大にして訂正しなかった。しかし、翌年鹿児島市竹迫団地の造成工事でボラすべり災害が発生したのである。シラスは垂直に切っても比較的安全だから垂直に切っていったが、ボラに突入してもそのまま垂直に切り進んでいった。恐らくどちらも軽石質で同じくシラスと呼ばれていたため、工法を変えようとは思いもしなかったのであろう。その結果、パートのおばさんが3人亡くなってしまった(写真)。もっと土木関係者に地質の知識を普及啓蒙しておくべきだったと後悔したことだった。そこで、混乱を回避するために、私は火砕流堆積物の非溶結部に限って使うことを提唱している。この意味のシラスで、鹿児島県で代表的なものは入戸火砕流堆積物である。県本土の半分以上を覆っている。
「シラス」か「しらす」か
「シラス」を仮名で表記するか平仮名で表記するかで論争があった。地理学の世界では戦前から「シラス台地」と仮名書きしていたから、国土地理院の地形図も仮名書きである。地質学関係もそれに則って昔から仮名書きとしてきた。学問の世界では先取権を尊重するのが当然だからである。もちろん、高校教科書や地学事典も仮名書きになっている。 ただ土質工学会(現地盤工学会)だけがシラスは外来語ではないし、仮名書きのシラスはうなぎなどの稚魚を指すとして、平仮名表記すると決めた。学会が正式に決めたので文部省学術用語集地学編も平仮名になっている。しかし、本項の標題を「シラスかしらすか」と表記すれば非常に読みにくい。平仮名の術語が地の文に埋没してしまっているからである。仮名は外来語を表記するだけでなく、「ボク」や「ダメ!」などのように地の文から際立たせ強調するためにも使う。土質工学会のような後発学会は一世紀の歴史を持つ地質学会や地理学会の先取権を尊重すべきであろう。それが学問の世界のルールである。本書は、一般の方を読者対象としているから、教科書で教わった通りに仮名書きとすることにした。なお、うなぎの本場浜松ではうなぎの稚魚を「しらす」と平仮名書きしている(写真)。
ただ土質工学会(現地盤工学会)だけがシラスは外来語ではないし、仮名書きのシラスはうなぎなどの稚魚を指すとして、平仮名表記すると決めた。学会が正式に決めたので文部省学術用語集地学編も平仮名になっている。しかし、本項の標題を「シラスかしらすか」と表記すれば非常に読みにくい。平仮名の術語が地の文に埋没してしまっているからである。仮名は外来語を表記するだけでなく、「ボク」や「ダメ!」などのように地の文から際立たせ強調するためにも使う。土質工学会のような後発学会は一世紀の歴史を持つ地質学会や地理学会の先取権を尊重すべきであろう。それが学問の世界のルールである。本書は、一般の方を読者対象としているから、教科書で教わった通りに仮名書きとすることにした。なお、うなぎの本場浜松ではうなぎの稚魚を「しらす」と平仮名書きしている(写真)。火砕流
 それではシラスの起源である火砕流とはどのようなものであろうか。昔は火砕流の説明をするのに苦労したものだが、今では雲仙普賢岳噴火のおかげで、「火砕流」という言葉はすっかり有名になった。1991年6月3日の火砕流(写真)で43名の方が亡くなったとき、新聞紙上では「大規模火砕流発生」と報じられた。しかし、地質学的にはこの程度の火砕流は極々ごく小規模で赤ん坊のようなものである。プレー型熱雲・メラピ型熱雲などと呼ばれるものがそれである。噴出量は極めて少なく0.01km3以下である。火山地質学で大規模火砕流と分類されるのは100km3を超す大量の火山灰や軽石を噴出してカルデラを作るようなものである。
それではシラスの起源である火砕流とはどのようなものであろうか。昔は火砕流の説明をするのに苦労したものだが、今では雲仙普賢岳噴火のおかげで、「火砕流」という言葉はすっかり有名になった。1991年6月3日の火砕流(写真)で43名の方が亡くなったとき、新聞紙上では「大規模火砕流発生」と報じられた。しかし、地質学的にはこの程度の火砕流は極々ごく小規模で赤ん坊のようなものである。プレー型熱雲・メラピ型熱雲などと呼ばれるものがそれである。噴出量は極めて少なく0.01km3以下である。火山地質学で大規模火砕流と分類されるのは100km3を超す大量の火山灰や軽石を噴出してカルデラを作るようなものである。火砕流は大量の高温粉体が重力により加速されて乱流として高速で移動する現象である。温度800℃度前後、秒速20~200mという。ガス圧で粒子が浮遊状態になり、見かけ粘性が低下して流動化するのであろう。いわば高温高速の灰かぐらだと思えばよい。
入戸火砕流を噴出した巨大噴火
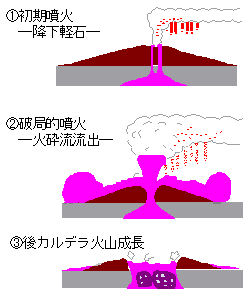 それでは鹿児島周辺に普遍的に見られる入戸火砕流堆積物はどのような噴火でもたらされたのだろうか。今から約25,000年前、氷河時代の真っ最中(主ウルム氷期)に、現鹿児島湾の奥部福山町沖で活動が始まった。若御子カルデラと呼ばれるところである。今でも海底火山活動が活発で火山ガスを盛んに噴出しており、地元ではタギリと呼んでいる。かつて姶良火山という2,000m級の高山が鹿児島湾にそびえていたが、大量のシラスを噴出した結果、陥没してカルデラ湾となったと考えられていたことがある。重富―磯間や垂水市牛根の急崖がそのカルデラ壁という訳である。しかし、若御子の部分を除いて大部分は基盤の四万十層群がごく浅いところに存在し、陥没したとは考えにくい。恐らく現在の鹿児島湾に沿う方向の断層群によりステップ状に落ち込んだ大規模な火山構造性地溝(鹿児島地溝)が形成され、その一部から噴火が始まったのであろう。
最初はまず軽石を大量に噴き上げた。冬だったのか北西風に乗って大隅半島を中心に大隅降下軽石が堆積した。厚いところで1mはあるから相当な量である。続いて火砕流が発生、国分隼人地区や鹿児島市など周辺地域を覆った。妻屋火砕流堆積物である。次に述べる入戸火砕流に覆われているため、不明な点が多いが、厚いところで数mの厚さがある。入戸火砕流に比べてやや細粒で軽石が少ない。その後、マグマが水と接触したのか横なぐりの爆風(サージ)が発生、岩片を周辺に吹き飛ばした。亀割坂角礫という。鹿児島市周辺でもごく薄いが見られることがある。しかし、これらの薄い岩片層は全部がサージ堆積物とは限らず、火砕流が流れる際地表の石を巻き込んで削り取ったものを途中で取り残してきたものも含まれているであろう。
それでは鹿児島周辺に普遍的に見られる入戸火砕流堆積物はどのような噴火でもたらされたのだろうか。今から約25,000年前、氷河時代の真っ最中(主ウルム氷期)に、現鹿児島湾の奥部福山町沖で活動が始まった。若御子カルデラと呼ばれるところである。今でも海底火山活動が活発で火山ガスを盛んに噴出しており、地元ではタギリと呼んでいる。かつて姶良火山という2,000m級の高山が鹿児島湾にそびえていたが、大量のシラスを噴出した結果、陥没してカルデラ湾となったと考えられていたことがある。重富―磯間や垂水市牛根の急崖がそのカルデラ壁という訳である。しかし、若御子の部分を除いて大部分は基盤の四万十層群がごく浅いところに存在し、陥没したとは考えにくい。恐らく現在の鹿児島湾に沿う方向の断層群によりステップ状に落ち込んだ大規模な火山構造性地溝(鹿児島地溝)が形成され、その一部から噴火が始まったのであろう。
最初はまず軽石を大量に噴き上げた。冬だったのか北西風に乗って大隅半島を中心に大隅降下軽石が堆積した。厚いところで1mはあるから相当な量である。続いて火砕流が発生、国分隼人地区や鹿児島市など周辺地域を覆った。妻屋火砕流堆積物である。次に述べる入戸火砕流に覆われているため、不明な点が多いが、厚いところで数mの厚さがある。入戸火砕流に比べてやや細粒で軽石が少ない。その後、マグマが水と接触したのか横なぐりの爆風(サージ)が発生、岩片を周辺に吹き飛ばした。亀割坂角礫という。鹿児島市周辺でもごく薄いが見られることがある。しかし、これらの薄い岩片層は全部がサージ堆積物とは限らず、火砕流が流れる際地表の石を巻き込んで削り取ったものを途中で取り残してきたものも含まれているであろう。最後に破局的な巨大噴火が発生、入戸火砕流を噴出した。恐らく成層圏にまで達する巨大な噴煙柱が空を焦がし、昼なお暗かったであろう。このとき成層圏にまで吹き上げた火山灰や軽石は折からの偏西風にのって、遠く東北地方から朝鮮半島にまで達した。私が学生時代、神奈川県の丹沢山にある丹沢パミスと呼ばれる10cmほどの軽石層を見たことがある。古富士山から来たのだろうか、箱根火山から来たのだろうかと議論をしたことを覚えている。これが姶良カルデラから飛んできた姶良Tn火山灰(AT)だったのである。
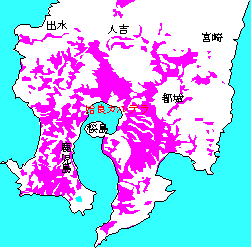 噴煙柱のうち比重の重い部分は周辺に雪崩下った。入戸火砕流である。北は熊本県人吉盆地、南は南薩地方、東は宮崎、西は吹上海岸にまで達しており、海抜1,000m程度の霧島山などは軽く乗り越えてしまった。厚いところで100mのシラス台地を形成しているから、その量たるや想像を絶する。2,000億トン以上と見積もられている。
噴煙柱のうち比重の重い部分は周辺に雪崩下った。入戸火砕流である。北は熊本県人吉盆地、南は南薩地方、東は宮崎、西は吹上海岸にまで達しており、海抜1,000m程度の霧島山などは軽く乗り越えてしまった。厚いところで100mのシラス台地を形成しているから、その量たるや想像を絶する。2,000億トン以上と見積もられている。これらの大量の火砕流がいったいどれくらいの時間かかって噴出したのだろうか。普通の地層なら100m積もるのに何万年、何百万年もかかるが、入戸火砕流は数時間から数週間で一気に積もったらしいという。大隅降下軽石の噴出から始まって入戸火砕流の流出まで一連の活動が数ヶ月から数年以内に起こったらしい。活動の休止期が長かったら、それぞれの地層の上面に古土壌など植生の繁茂や風化の進行を示す証拠があるはずだが、そうした証拠は見つかっていないからである。
このような世界でもまれな超大型の火山活動があった以上、当然、当時いた人間も動植物も絶滅し、南九州は死の世界になったであろう。実際、喜入町の帖地遺跡では旧石器遺構がシラスに覆われている。噴出源に近い鹿児島湾周辺は高温だったから、遺体も残らず蒸発してしまったに違いない。人吉など遠隔地では、ポンペイ最後の日みたいに、遺体が埋もれているかも知れないが。また、成層圏に噴き上げた大量の火山灰はジェット気流に乗って世界中を回り、寒冷な気候をもたらしたに違いない。この活動が原因でウルム氷期の最盛期をもたらしたとは言えないかも知れないが、寒冷化を加速したことは確かであろう。
積もったばかりの火砕流堆積物は、まだ熱く時々ガスを吹き上げたり、二次的な爆発を起こしたりするが、やがて空気に冷やされて表面から冷却する。これが火砕流堆積物の非溶結部、つまりシラスである。地面と接している最下底の部分もやはり地面から冷やされ、非溶結になる。
 なお、本書の本筋とは関係ないが、シラスと密接に関係する溶結凝灰岩についても触れておく。堆積物が極端に厚いところ、とくに火砕流が狭い谷筋に流れ込んだところでは、熱がこもってなかなか冷えない。中心部分は自分自身の熱と荷重のため、圧密してくっつく。溶結凝灰岩である。軽石はつぶれてレンズ状の黒曜石になる。横から見ると黒くて短かい縞模様に見え、なかなかきれいである。ユータキシティック構造という。元々シラスと同起源、それほど硬くない。昔の技術でも加工しやすかったから、石材として利用された。風化しやすくもろいので先祖代々伝える墓石には向かない。主として石塀や敷石などに使われた。有名な甲突川の石橋も付近に産出する溶結凝灰岩で作られている。
なお、本書の本筋とは関係ないが、シラスと密接に関係する溶結凝灰岩についても触れておく。堆積物が極端に厚いところ、とくに火砕流が狭い谷筋に流れ込んだところでは、熱がこもってなかなか冷えない。中心部分は自分自身の熱と荷重のため、圧密してくっつく。溶結凝灰岩である。軽石はつぶれてレンズ状の黒曜石になる。横から見ると黒くて短かい縞模様に見え、なかなかきれいである。ユータキシティック構造という。元々シラスと同起源、それほど硬くない。昔の技術でも加工しやすかったから、石材として利用された。風化しやすくもろいので先祖代々伝える墓石には向かない。主として石塀や敷石などに使われた。有名な甲突川の石橋も付近に産出する溶結凝灰岩で作られている。また、溶結凝灰岩もいずれ冷却する。その時、熱収縮に伴って割れ目が発達する。粘土のひび割れ(この場合は乾燥脱水収縮)と同じく六角形に割れることが多い。柱状節理という。切り立った急崖をなす溶結凝灰岩が転倒崩壊(トップリング)するのは、この柱状節理の存在が災いしているのである。
シラスの特徴
 シラスは火砕流堆積物であるから、灰かぐらのように流れたことに由来する特徴を有する。第一の特徴は、淘汰が悪い(粒径が不揃い)ということである。大小さまざまの軽石や岩片と細かな火山灰とが種々雑多に混ざり合っている。火山灰とは、結晶する時間もなく急冷された火山ガラスである。普通の砂のように川で流されているうちに角が取れて丸くなった石英や長石の結晶とは違う。鋭利に尖ったガラス片がかみ合って、軽石や岩片の間を埋めているのだから、結構強度がある。シラスの崖が垂直でも結構もつ理由である。非溶結とはいえ、多少とも熱で溶結しているのだとの説もある。水を含むと角砂糖のごとく溶けるとの俗説があるが、そのようなことはない。水を含んだだけでもろく崩れるようなら、二万年もシラス台地が保つはずがない。今頃は大平原になっていて鹿児島は豊かな穀倉地帯になっていたであろう。事実は残念ながら水田に不適なところばかりである。
シラスは火砕流堆積物であるから、灰かぐらのように流れたことに由来する特徴を有する。第一の特徴は、淘汰が悪い(粒径が不揃い)ということである。大小さまざまの軽石や岩片と細かな火山灰とが種々雑多に混ざり合っている。火山灰とは、結晶する時間もなく急冷された火山ガラスである。普通の砂のように川で流されているうちに角が取れて丸くなった石英や長石の結晶とは違う。鋭利に尖ったガラス片がかみ合って、軽石や岩片の間を埋めているのだから、結構強度がある。シラスの崖が垂直でも結構もつ理由である。非溶結とはいえ、多少とも熱で溶結しているのだとの説もある。水を含むと角砂糖のごとく溶けるとの俗説があるが、そのようなことはない。水を含んだだけでもろく崩れるようなら、二万年もシラス台地が保つはずがない。今頃は大平原になっていて鹿児島は豊かな穀倉地帯になっていたであろう。事実は残念ながら水田に不適なところばかりである。第二の特徴は、低いところを埋めるように分布するということである。流体のように流れる以上、低きにつくのは当然だから、谷を埋め低地を覆う。大隅半島ではシラスの中に基盤岩の低い山が散在している。当時の山々がシラスで裾野を埋め尽くされ、山頂部が取り残された姿である。
 第三の特徴は、流水の浸食に弱いということである。軽石は文字通り軽くて水に浮くし、全体として比重が小さい。そのため、流水の浸食作用には極めて弱い。道路の法面工事で折角きれいに整形しても、コンクリート吹き付けする前に雨が降ったりすると、すぐリル(雨裂)ができ、少し放置するとガリに発達する。自然状態では、狭く深い切り立った谷が発達する。知覧城(左写真)のような中世の山城は、こうした天然の地形を巧みに利用して要害としていた。
第三の特徴は、流水の浸食に弱いということである。軽石は文字通り軽くて水に浮くし、全体として比重が小さい。そのため、流水の浸食作用には極めて弱い。道路の法面工事で折角きれいに整形しても、コンクリート吹き付けする前に雨が降ったりすると、すぐリル(雨裂)ができ、少し放置するとガリに発達する。自然状態では、狭く深い切り立った谷が発達する。知覧城(左写真)のような中世の山城は、こうした天然の地形を巧みに利用して要害としていた。第四の特徴は、言わずもがなシラス台地(火砕流台地)の形成である。鹿児島の地形を代表する。
第五の特徴は地下水の貯留層となっていることである。火山灰などで隙間を埋められているとはいえ、普通の砂岩や泥岩に比べれば、空隙が多い。そこに地下水が蓄えられている。シラス台地周縁の崖下ではシラスの下からこんこんと清水が湧き出しており、夏でも涸れることがない。昔からこれを水源として利用してきた。鹿児島の河川は小さな川が多いのに、夏も涸れないのはシラス台地から水が補給されているからである。
本ページ先頭|従来シラスと称されてきたもの|「シラス」か「しらす」か|火砕流|入戸火砕流を噴出した巨大噴火|シラスの特徴
連絡先:iwamatsu@sci.kagoshima-u.ac.jp 更新日:1996年10月13日