『シラス災害―災害に強い鹿児島をめざして―』
岩松 暉 著
第1章 鹿児島の自然災害
鹿児島県本土の地学的特徴|戦後の主な自然災害|最近の被害統計
鹿児島県本土の地学的特徴
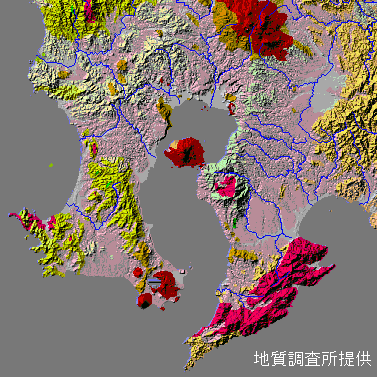 左図は鹿児島県本土の地質図である。基盤には白亜系四万十層群(緑色と黄緑色)および古第三系日南層群(橙色)が広く分布している。これらの地層は、地質時代が古いから堅硬で、とくに砂岩は砕石として使われている。しかし、海底地すべり堆積物など剥がれやすい片状岩も含まれており、地すべりを起こすことがしましばある。それらを中新世の花崗岩類(赤色)が貫く。大隅花崗岩・高隈山花崗岩・紫尾山花崗岩などがそれである。墓石などの石材に多用されている御影石と同じものである。これらの古い地層や岩体を新第三系の北薩層群や南薩層群の主として火山岩類(薄黄色)が覆う。菱刈や串木野の金山が胚胎する地層である。それらすべてを覆ってシラス(ピンク色)が県本土の約6割に分布する。火砕流堆積物で、がけ崩れを起こしやすい。最後に霧島山・桜島・開聞岳の活火山(茶色)が北北東―南南西に連なる。古生層や変成岩はほとんど存在せず、概して若い地層が多いのが特徴である。この図で何よりもシラスが目立つ。シラス災害が多い所以である。地形的には活火山が1,000m級の独立峰をなし、それほど高い山脈はない。
左図は鹿児島県本土の地質図である。基盤には白亜系四万十層群(緑色と黄緑色)および古第三系日南層群(橙色)が広く分布している。これらの地層は、地質時代が古いから堅硬で、とくに砂岩は砕石として使われている。しかし、海底地すべり堆積物など剥がれやすい片状岩も含まれており、地すべりを起こすことがしましばある。それらを中新世の花崗岩類(赤色)が貫く。大隅花崗岩・高隈山花崗岩・紫尾山花崗岩などがそれである。墓石などの石材に多用されている御影石と同じものである。これらの古い地層や岩体を新第三系の北薩層群や南薩層群の主として火山岩類(薄黄色)が覆う。菱刈や串木野の金山が胚胎する地層である。それらすべてを覆ってシラス(ピンク色)が県本土の約6割に分布する。火砕流堆積物で、がけ崩れを起こしやすい。最後に霧島山・桜島・開聞岳の活火山(茶色)が北北東―南南西に連なる。古生層や変成岩はほとんど存在せず、概して若い地層が多いのが特徴である。この図で何よりもシラスが目立つ。シラス災害が多い所以である。地形的には活火山が1,000m級の独立峰をなし、それほど高い山脈はない。気象学的には、北西太平洋季節風帯(モンスーン帯)に位置し、梅雨前線が停滞しやすく、梅雨末期にしばしば集中豪雨に見舞われる。また、台風通路の玄関口にも当たるため、洋上で発達した台風が陸地にぶつかって減衰することなく、直接襲うところでもある。いずれにせよ、地質・気象の両面から、鹿児島は土砂災害に襲われやすい要因を持っているありがたくないお国柄である。
戦後の主な自然災害
上述のような自然条件にあるため、鹿児島はしばしば大災害に見舞われている。戦後の災害で死者の多かった災害はルース台風の209名および枕崎台風の129名が特筆される。以下は被害額(単位:百万円)の記録である。なお、通常は1993年鹿児島大災害として一括される災害が上位に5個所も分散して掲載されている。6月から9月までの一連の災害を一括すればダントツになる。| 順位 | 発生年月日 | 災害種別 | 主な被害地域 | 被害額 |
| 1 | 1993.9.1-3 | 台風13号 | 全域 | 917.5 |
| 2 | 1993.8.5-6 | 集中豪雨 | 鹿児島地方 | 801.8 |
| 3 | 1993.7.31-8.2 | 集中豪雨 | 鹿児島地方 | 639.5 |
| 4 | 1989.7.27-28 | 台風11号 | 県本土・熊毛 | 508.8 |
| 5 | 1993.6.12-7.8 | 集中豪雨 | 全域 | 416.1 |
| 6 | 1951.10.14 | ルース台風 | 全域 | 332.2 |
| 7 | 1985.8.30-31 | 台風13号 | 薩摩 | 309.6 |
| 8 | 1976.9.7-13 | 台風17号 | 全域 | 261.5 |
| 9 | 1976.6.22-26 | 梅雨前線 | 全域 | 252.2 |
| 10 | 1990.9.16-19 | 台風19号 | 全域 | 218.9 |
| 11 | 1991.9.25-28 | 台風19号 | 全域 | 209.1 |
| 12 | 1993.8.8-10 | 台風7号 | 全域 | 202.4 |
| 13 | 1971.8.3-5 | 台風19号 | 屋久島等 | 201.1 |
| 14 | 1977.9.9-10 | 沖永良部台風 | 熊毛・大隅 | 196.2 |
| 15 | 1955.9.28-30 | 台風22号 | 熊毛・大隅 | 189.5 |
最近の被害統計
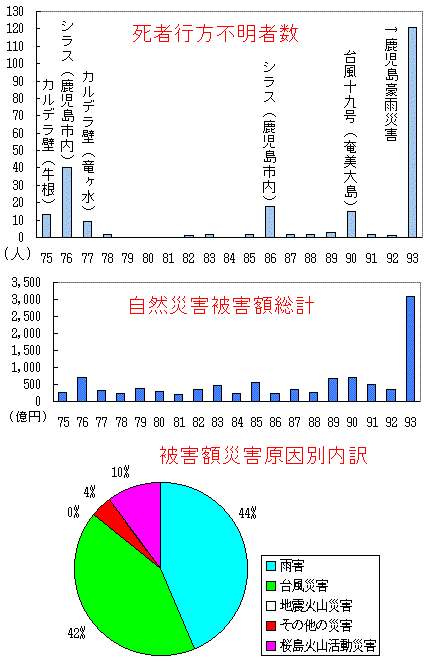 最近でも10年弱に1回くらいの割合で大きな災害に見舞われている。ほとんどが梅雨末期の集中豪雨や台風に伴う雨災害である。中でも鹿児島市を中心とするシラス災害や姶良カルデラ壁の土石流災害が死者を多数出している。台風による被害は強風災害のため、飛来物や落下物による怪我など軽傷者が多い。被害額も年平均535億円と莫大な額に上っている。こんな巨額のお金が飛んでしまうくらいなら、事前の防災投資に思い切った額を割いたほうが、はるかに得策だと思うがいかがだろうか。
最近でも10年弱に1回くらいの割合で大きな災害に見舞われている。ほとんどが梅雨末期の集中豪雨や台風に伴う雨災害である。中でも鹿児島市を中心とするシラス災害や姶良カルデラ壁の土石流災害が死者を多数出している。台風による被害は強風災害のため、飛来物や落下物による怪我など軽傷者が多い。被害額も年平均535億円と莫大な額に上っている。こんな巨額のお金が飛んでしまうくらいなら、事前の防災投資に思い切った額を割いたほうが、はるかに得策だと思うがいかがだろうか。
本ページ先頭|鹿児島県本土の地学的特徴|戦後の主な自然災害|最近の被害統計
連絡先:iwamatsu@sci.kagoshima-u.ac.jp 更新日:1996年10月13日