『シラス災害―災害に強い鹿児島をめざして―』
岩松 暉 著
第3章 シラス災害の歴史的変遷
守護町の後裔|シラス台地の地形と土地利用|江戸時代の土地制度|戦後のシラス災害|シラス災害の種類
まえがきでシラス災害宿命論に疑問を呈しておいた。確かに鹿児島はシラス地帯である。昔から今のように大きな被害を被っていたのであろうか。少し歴史的に振り返ってみたい。
守護町の後裔
県庁所在地のような大都市は開けた平野に位置しているのが普通である。明治の開港場もあるが、多くは近世の城下町が発展したものである。どうして鹿児島のように猫の額ほどの平地しかない場所に53万都市があるのか不思議である。戦国時代、他の地方は下克上で領主が目まぐるしく入れ替わり、その都度戦火に焼かれて破壊と建設が繰り返された。中世の山城から近世の平城へと当時の戦闘様式の変化と共に居を移したり、経済活動に好都合な都市計画を実施したりして、時代にマッチしたものに変化してきたのである。しかし、島津氏ひとり鎌倉から明治に至るまで領主が入れ替わることなく統治し続けてきた。幸か不幸か中央から隔絶していたため、政争に巻き込まれずに済んだのであろう。
 律令時代には開けて豊かな穀倉地帯である国分と川内に国府があった。島津氏がここを三州支配の拠点とすることなく、東福寺城(鹿児島市多賀山公園)に拠ったのは、大隅・薩摩両国ににらみを利かすのには中央にあって都合がよかったのが原因であろうが、山城に立てこもってゲリラ的に出撃する当時の戦闘様式にも好都合だったからであろう。大隅方面からの敵にはカルデラ壁の天険があり、肥後方面からの敵には河頭の峡谷がある。どんな大軍が攻めてきても、小部隊で食い止めることができる。南の海上ルートに対しては、浮沈艦桜島が控え、敵の水軍を背後から挟撃できた。まさに万全の備えのある要害の地である。しかし、天険の地はイコール災害地でもある。確かに多賀山の山城から平場の鶴丸城に移ったとはいえ、狭い鹿児島の中での移動であって、本質的には中世の守護町がそのまま大きくなったに過ぎない。鹿児島が災害にしばしば襲われる遠因はここにある。
律令時代には開けて豊かな穀倉地帯である国分と川内に国府があった。島津氏がここを三州支配の拠点とすることなく、東福寺城(鹿児島市多賀山公園)に拠ったのは、大隅・薩摩両国ににらみを利かすのには中央にあって都合がよかったのが原因であろうが、山城に立てこもってゲリラ的に出撃する当時の戦闘様式にも好都合だったからであろう。大隅方面からの敵にはカルデラ壁の天険があり、肥後方面からの敵には河頭の峡谷がある。どんな大軍が攻めてきても、小部隊で食い止めることができる。南の海上ルートに対しては、浮沈艦桜島が控え、敵の水軍を背後から挟撃できた。まさに万全の備えのある要害の地である。しかし、天険の地はイコール災害地でもある。確かに多賀山の山城から平場の鶴丸城に移ったとはいえ、狭い鹿児島の中での移動であって、本質的には中世の守護町がそのまま大きくなったに過ぎない。鹿児島が災害にしばしば襲われる遠因はここにある。シラス台地の地形と土地利用
シラスは空隙に富むから、シラス台地は水に乏しい。降った雨はすぐスーッと浸み込んでしまうからである。しかし、逆に台地全体としてはかなりの保水力があり、一種の水瓶の役割を果たしている。夏でも台地下からきれいな水が湧き出す。当然、灌漑の発達していなかった昔は、台地上は原野のまま放置され、集落はがけ下の湧水を求めて立地した。しかし、がけ下はがけ崩れの危険がある。どのようにして利用したのであろうか。 地下水はシラスの最下底、基盤との境目(不整合という)に存在する。基盤の堆積岩などが不透水層の役割を果たすからである。この不整合面ががけに直接露出している場合には、そこから泉が湧き出すが、一般にはがけ下にはがけ崩れの土砂(崩積土)が堆積している。崖錐という。なだらかな坂の部分である。したがって、地下水はこの崖錐の部分を伏流して末端に湧き出す。ここに家を構えれば飲料水が得られる。崖錐の部分は傾斜地だし地表は水に乏しいから、雑木林のまま放置して薪炭の供給地としたか、せいぜい畑地くらいにしか利用しなかった。ここを避けたのは、崖錐が崩積土の堆積地形で、がけ崩れの際土砂が到達する危険があると知っていたのかどうかわからないが、巧まずしてがけ崩れの危険地から遠ざかって住んでいたのである。水田はそれより標高の低いところ、谷川沿いの狭い谷底平野(迫・谷地・谷津)に立地していた。
地下水はシラスの最下底、基盤との境目(不整合という)に存在する。基盤の堆積岩などが不透水層の役割を果たすからである。この不整合面ががけに直接露出している場合には、そこから泉が湧き出すが、一般にはがけ下にはがけ崩れの土砂(崩積土)が堆積している。崖錐という。なだらかな坂の部分である。したがって、地下水はこの崖錐の部分を伏流して末端に湧き出す。ここに家を構えれば飲料水が得られる。崖錐の部分は傾斜地だし地表は水に乏しいから、雑木林のまま放置して薪炭の供給地としたか、せいぜい畑地くらいにしか利用しなかった。ここを避けたのは、崖錐が崩積土の堆積地形で、がけ崩れの際土砂が到達する危険があると知っていたのかどうかわからないが、巧まずしてがけ崩れの危険地から遠ざかって住んでいたのである。水田はそれより標高の低いところ、谷川沿いの狭い谷底平野(迫・谷地・谷津)に立地していた。シラス台地上に集落ができるようになったのは、ずっと遅れて近世になってからである。それでも数10mもの深井戸を掘って牛馬に釣瓶を引かせるなど、水を得るためには大変な苦労があったという(写真)。
江戸時代の土地制度
 古代は人口が少なかったから、土砂災害はあまり問題にならなかったであろう(もちろん、干ばつや台風あるいは虫害など、まだ生産力の低かった農業に決定的なダメージを与える災害はあった)。しかし、人口がかなり増えてきた江戸時代、人々は土砂災害とどのようにつき合ってきたのだろうか。薩摩藩には門割制度という独特の土地制度がある。村をいくつかの門に分ける。門は1名の名頭と2~5名の名子からなる。年貢は個人で請け負うのではなく門請制である。連帯責任だから確実な年貢徴収が保障されるので、藩側の利益から創設されたのだろうが、農民から見ても都合のよい面もあった。同時に門割制がとられたからである。一定の決まった私有地を耕すのではなく、数年に一度クジで土地を割り替える制度である。私有地なら災害に遭うと決定的ダメージを受け、なかなか立ち直れず逃散するしかない。しかし、門割制なら門全体の援助で復旧できるし、遠からず肥沃な土地と交換してもらえる。つまり、災害の危険分散、均等負担である。なお、特筆すべきことは、土地割り替えに際して洗出(あれだし)と呼ばれるシラス台地を刻む谷の出口を避けたことである。ここは土石流扇状地であり、土石流災害に見舞われやすいことを経験的に知っていたのであろう。
古代は人口が少なかったから、土砂災害はあまり問題にならなかったであろう(もちろん、干ばつや台風あるいは虫害など、まだ生産力の低かった農業に決定的なダメージを与える災害はあった)。しかし、人口がかなり増えてきた江戸時代、人々は土砂災害とどのようにつき合ってきたのだろうか。薩摩藩には門割制度という独特の土地制度がある。村をいくつかの門に分ける。門は1名の名頭と2~5名の名子からなる。年貢は個人で請け負うのではなく門請制である。連帯責任だから確実な年貢徴収が保障されるので、藩側の利益から創設されたのだろうが、農民から見ても都合のよい面もあった。同時に門割制がとられたからである。一定の決まった私有地を耕すのではなく、数年に一度クジで土地を割り替える制度である。私有地なら災害に遭うと決定的ダメージを受け、なかなか立ち直れず逃散するしかない。しかし、門割制なら門全体の援助で復旧できるし、遠からず肥沃な土地と交換してもらえる。つまり、災害の危険分散、均等負担である。なお、特筆すべきことは、土地割り替えに際して洗出(あれだし)と呼ばれるシラス台地を刻む谷の出口を避けたことである。ここは土石流扇状地であり、土石流災害に見舞われやすいことを経験的に知っていたのであろう。
戦後のシラス災害
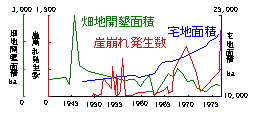 昭和初期までは基本的にそれ以前と同様の土地利用形態だった。つまり、災害を避け災害と共存していたから、がけ崩れが災害として認識されることはあまりなかった。シラス災害が有名になったのは戦後のことである。1949年(昭和24年)のデラ台風・ジュディス台風による豪雨災害からである。図に戦後のがけ崩れ発生件数を示した。ただし、人的物的被害のあった災害だけで、被害のなかったがけ崩れは含まれていない。
昭和初期までは基本的にそれ以前と同様の土地利用形態だった。つまり、災害を避け災害と共存していたから、がけ崩れが災害として認識されることはあまりなかった。シラス災害が有名になったのは戦後のことである。1949年(昭和24年)のデラ台風・ジュディス台風による豪雨災害からである。図に戦後のがけ崩れ発生件数を示した。ただし、人的物的被害のあった災害だけで、被害のなかったがけ崩れは含まれていない。図から明らかに2回の多発期を読みとることができる。第一のピークは1950年代の前半に存在する。どうしてこの時期に災害が頻発したのであろうか。「国破れて山河あり」というが、戦争中はどうしても治山治水が疎かになる。このツケがまわったことも一因であろう。しかし、何よりも戦後シラス台地が大々的に開墾されたことが大きい。敗戦により海外領土を失って、大量の引揚者や復員兵が狭い四つの島にあふれた。食糧増産のかけ声の下、鹿児島県でも畑地開墾面積が急増した。シラス台地を切り開いてカライモ(サツマイモ)を植えたのである。台地上の植生被覆を大規模に剥ぎ、農道を設置するなどして表面流水を生じやすくしたのが原因で、シラスの浸食崩壊を引き起こした。落水型浸食やがけ脚洗掘などがけ崩れというよりはむしろ浸食による災害が多かった(図左)。主として農村地帯で発生したから、この時期の災害は農地災害の範ちゅうに属し、人的被害は少ない。
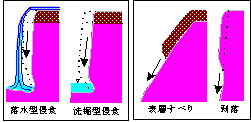 この第一のピークの災害は大規模だったから世間の注目を浴び、土木技術者の関心を呼んだ。台地上には暗きょなど排水施設を設けて流水が生じるのを防いだ。谷には砂防ダムが入れられ、台地下の河川には床固工が施された。こうして1956年から1965年にかけての10年間はシラス災害はピタリと止んでしまった。この間、雨量が特別少なかった訳ではないから、土木技術の勝利と言える。
この第一のピークの災害は大規模だったから世間の注目を浴び、土木技術者の関心を呼んだ。台地上には暗きょなど排水施設を設けて流水が生じるのを防いだ。谷には砂防ダムが入れられ、台地下の河川には床固工が施された。こうして1956年から1965年にかけての10年間はシラス災害はピタリと止んでしまった。この間、雨量が特別少なかった訳ではないから、土木技術の勝利と言える。しかし、がけ崩れの少ない時期はわずか10年で終わり、再び多発する傾向をみせて現在に至っている。この第二のピークの時期は、わが国経済の高度成長期と一致する。全国的に人口の農村部から都市部への集中が起こった。鹿児島県においても例にもれず、農村部の過疎進行と、鹿児島市の人口急増となって表れた。これに伴って、宅地面積も1966年頃から急速に増加する。しかも県全体の伸びに対する市部の伸びの割合が平均約62%であるから、いかに市部で宅地造成が大規模に行われたか理解できよう。平野の少ない鹿児島では必然的に傾斜地や山地へ立地するようになり、シラス斜面に人工の手が加えられていった。こうして第二のピークの災害は、都市災害・宅地災害へと変貌する。人命の犠牲を伴うようになったのである。
同時に、がけ崩れの形態もまた変化していった。大規模な浸食による災害が減少し、代わって表層すべりや盛土など人工法面の崩壊などが増えてきた(図右)。 このように土地利用形態の変化と土木技術の進歩とが相拮抗しながら、災害はその様相を変化させてきている。
シラス災害の種類
以上、戦後のシラス災害について簡単に触れてきた。がけ崩れの様式も浸食から表層すべりへと変化したと述べたけれども、大局的には間違いないが、実際にはさまざまな形態があった。最近見られるのは、ボラすべり・風化土層の表層すべりおよび浮きシラスの土砂流である。以下、この代表的な災害について、具体例に則しながら解説してみたい。やはり、私が最初に経験したボラすべり災害から始めることとする。本ページ先頭|守護町の後裔|シラス台地の地形と土地利用|江戸時代の土地制度|戦後のシラス災害|シラス災害の種類
連絡先:iwamatsu@sci.kagoshima-u.ac.jp 更新日:1996年10月13日