『地すべり学入門』
岩松 暉 著
第6章 地すべりの運動様式
1.変位計測による運動の実態
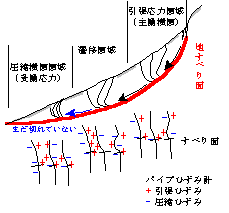 福本・他(1980)は新潟県四十刈地すべり地にパイプひずみ計を埋め込んで観測した。土塊の移動は斜面上部の滑落崖から始まり、下方に向かってすべり面を形成しながら進行性破壊をする。したがって、すべり面付近の変位は地表付近より著しく大きく、地表での伸縮計観測で変位が確認されたときには、かなり破壊が進行していることを意味する。下方の圧縮応力領域では変位が非常に小さく、まだすべり面は形成されていない。
福本・他(1980)は新潟県四十刈地すべり地にパイプひずみ計を埋め込んで観測した。土塊の移動は斜面上部の滑落崖から始まり、下方に向かってすべり面を形成しながら進行性破壊をする。したがって、すべり面付近の変位は地表付近より著しく大きく、地表での伸縮計観測で変位が確認されたときには、かなり破壊が進行していることを意味する。下方の圧縮応力領域では変位が非常に小さく、まだすべり面は形成されていない。
2.植物指標からみた運動の実態
◎地表変動に関する植物指標
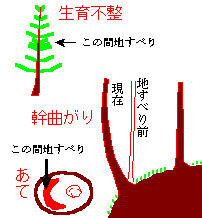 植物は動物と違って移動できないから、場の環境因子に強く支配されて生育する。路傍のムラサキツユクサが大気汚染のよい指標になることは広く知られている。しかし、地文要因の把握には、寿命の短い草本よりも木本が適している。例えば、地すべりが発生して樹木の根が断ち切られると、栄養補給が不十分になるから、その時だけ生育不整が起こる。松などは年に1回枝を出す(ただし、南九州以南では年2回芽を出すことがある)から樹冠不整の見られた年は、地すべりがあった証拠となる(左図上)。また、樹木は背地性があるから、地面がクリープして倒れると、立ち直ろうとして根曲がりを起こす(左図下)。当然、ストレスを受けながら生長するから、その年の年輪は異常発育し、夏材が赤くなる。あてred woodという。あての年輪解析から、地すべりの年代がわかる。ただし、雪国では雪の重みや雪崩などでも根曲がりを起こすから注意が必要である。
植物は動物と違って移動できないから、場の環境因子に強く支配されて生育する。路傍のムラサキツユクサが大気汚染のよい指標になることは広く知られている。しかし、地文要因の把握には、寿命の短い草本よりも木本が適している。例えば、地すべりが発生して樹木の根が断ち切られると、栄養補給が不十分になるから、その時だけ生育不整が起こる。松などは年に1回枝を出す(ただし、南九州以南では年2回芽を出すことがある)から樹冠不整の見られた年は、地すべりがあった証拠となる(左図上)。また、樹木は背地性があるから、地面がクリープして倒れると、立ち直ろうとして根曲がりを起こす(左図下)。当然、ストレスを受けながら生長するから、その年の年輪は異常発育し、夏材が赤くなる。あてred woodという。あての年輪解析から、地すべりの年代がわかる。ただし、雪国では雪の重みや雪崩などでも根曲がりを起こすから注意が必要である。いずれにせよ、樹木年代学は1~103年オーダーの現象を定量的に捉えるのに適しており、地質学にないタイムスケールである。地質屋も大いに取り入れる必要があろう。
◎生育不整からみた造林地のクリープ現象
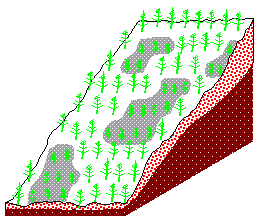 東(1979)は造林地の生育不整の分布から、地すべりが一斉に移動するのではなく、ブロック状に移動することを見出した。
東(1979)は造林地の生育不整の分布から、地すべりが一斉に移動するのではなく、ブロック状に移動することを見出した。
3.地すべり土塊の性質と運動様式
 崩壊物質のレオロジカルな性質は当然崩壊型式に対応する。植村(1976)は左図のような概念図を描いた。ここで延性度ductilityとは、岩石力学の概念で、岩石が破壊するまでにひずんだひずみ量%である。延性度が高いほど流動性に富んでいる。例えば、砂岩は泥岩に比べて延性度が低く脆性的に振る舞う。平均延性度は、砂岩泥岩互層を例に取ると、砂岩優勢だと低く、逆に泥岩優勢だと高い。延性度較差は、構成岩石の延性度の差だから、砂岩泥岩互層のほうが砂岩シルト岩互層よりも、コントラストが高い。
崩壊物質のレオロジカルな性質は当然崩壊型式に対応する。植村(1976)は左図のような概念図を描いた。ここで延性度ductilityとは、岩石力学の概念で、岩石が破壊するまでにひずんだひずみ量%である。延性度が高いほど流動性に富んでいる。例えば、砂岩は泥岩に比べて延性度が低く脆性的に振る舞う。平均延性度は、砂岩泥岩互層を例に取ると、砂岩優勢だと低く、逆に泥岩優勢だと高い。延性度較差は、構成岩石の延性度の差だから、砂岩泥岩互層のほうが砂岩シルト岩互層よりも、コントラストが高い。次に崩壊型式だが、次のようにまとめられる。
- Flow…急速混濁乱流
- 崩積土が水を含んだ場合など
- Creep…緩慢塑性流動
- 第三紀層黒色泥岩の地すべりなど
- Slide…脆性破壊・急速滑落
- 第三紀層砂岩泥岩互層の地すべりなど
- Fall…粉体移動
- マサ土の崩落など
連絡先:iwamatsu@sci.kagoshima-u.ac.jp 更新日:1997年1月1日