なお、「かだいおうち」は日本における大学研究室ホームページの第1号です。歴史的遺産としてここにアーカイブしておきます。
 鹿児島の大規模土工と地質
鹿児島の大規模土工と地質
新幹線紫尾山トンネル|串木野地下石油備蓄|喜界島地下ダム|鹿屋シラス分水路トンネル|早咲大橋|志布志国家石油備蓄基地
鹿児島県はシラスで有名ですが、実はそれ以外にもいろいろな地質が分布しています。そうした地質の特性に応じ、近年全国的な意義のある著名な大規模土木工事が行われています。さながら土木地質の実験地の観があります。以下、代表的な例を見てみましょう。
 新幹線紫尾山トンネル―白亜紀四万十層群―
新幹線紫尾山トンネル―白亜紀四万十層群―
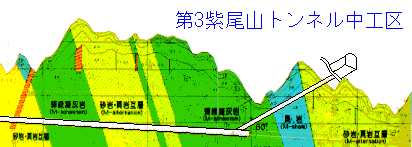 鉄建公団パンフより
鉄建公団パンフより
難工事区間として事前着工が認められたところです。北薩四万十帯の緑色岩および砂岩頁岩互層中に掘られました。緑色岩類は枕状溶岩・ピローブレッチャ・ハイアロクラスタイトと岩相変化が激しく、節理等の亀裂が発達するため、湧水に悩まされたそうです。
 串木野地下石油備蓄基地―新第三紀火山岩類―
串木野地下石油備蓄基地―新第三紀火山岩類―
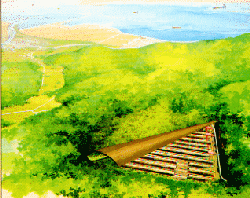 日本地下石油備蓄(株)パンフより
日本地下石油備蓄(株)パンフより
横穴水封式地下備蓄基地です。水封式とは、地下水圧を貯蔵原油や蒸発ガスの圧力より高くすることにより、油漏れやガス漏れを防ぐ方法です。地質は新第三紀北薩安山岩類の自破砕状安山岩と礫岩からなっています。火山岩類は地表では亀裂が無数に発達するのが普通ですが、ここの地下では極めて良好な岩盤をなしていました。
 喜界島地下ダム―琉球石灰岩―
喜界島地下ダム―琉球石灰岩―
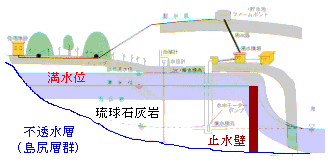 喜界島地下ダム模式断面図(九州農政局パンフより)
喜界島地下ダム模式断面図(九州農政局パンフより)
喜界島は標高の低い小さな島ですから、大きな河川がなく慢性的な水不足に悩まされています。そこで、空隙の多い琉球石灰岩の中に雨水を貯留しておこうと、地下ダムが計画されました。琉球石灰岩堆積前の旧地形、つまり第三紀島尻層群の不整合面を洗面器に見立て、下流側に地中壁を作って水を溜めようという訳です。
 鹿屋分水路トンネル―シラス―
鹿屋分水路トンネル―シラス―
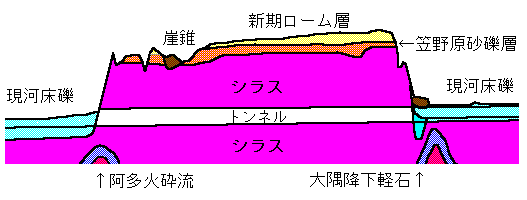 露木・他(1988)より
露木・他(1988)より
シラスは崩れやすいとしてトンネルを掘るのは避けてられきました。本格的なシラストンネルは、鹿児島市の武岡トンネルなど九州自動車道や国道バイパスのトンネルとして建設されました。いずれも地下水位よりも高い位置に計画され、NATM工法で施工されました。もっとも困難な地下水面下のシラストンネルとしては、鹿屋分水路が有名です。大部分シラス(入戸火砕流)中を通りますが、一部に大隅降下軽石が存在するため、内部浸食が問題になりました。
 早咲大橋―姶良火山岩類―
早咲大橋―姶良火山岩類―
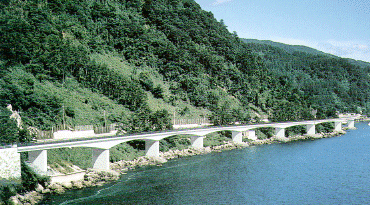 建設省大隅工事事務所パンフより
建設省大隅工事事務所パンフより国道220号の垂水市海潟~牛根間は、姶良火山の火山岩や火砕流からなる急崖になっています。そのため、集中豪雨の度に斜面崩壊が発生して交通が途絶します。そこで、建設省では現在の道路を放棄して海上を橋梁で通すことにしました。この急崖の上は早崎あるいは咲花平(さっかびら)と呼ばれていた台地ですので、早咲大橋と名付けられました。全長888mもあります。咲花平は新鉱物の大隅石が記載されたところとしても有名です。なお、欄干には軍艦マーチの楽譜がレリーフとして飾ってあります。作曲者が垂水市出身なのだそうです。1997年12月には完成します。牛根側は一旦桜島に渡った後、橋で大隅半島のほうに戻る計画とのことです。
 志布志湾国家石油備蓄基地―沖積層―
志布志湾国家石油備蓄基地―沖積層―
 志布志石油備蓄(株)パンフより
志布志石油備蓄(株)パンフより
地上タンク式の国家石油備蓄基地です。わが国石油消費量の8日分を溜めることができるそうです。肝属川河口の沖合いに埋立地を造成して建設されました。地質は、シラス(入戸火砕流堆積物)を基盤とし、上部洪積層とされる志布志湾層と肝属川の埋没谷を埋める沖積層からなっています。埋土層の厚さは15m程度ですが、シラス地帯を後背地にもつことから、砂質土的で粘着力はほとんどゼロ、内部摩擦角が大きいという特徴があります。そのため、地盤改良としてプレロード工法(備蓄する油と同重量の土砂を事前に積み上げ、圧密を促進させる方法)が採用され、地震時の液状化対策としてサンドコンパクションによる締固め工法が採られました。
ページ先頭|新幹線紫尾山トンネル|串木野地下石油備蓄|喜界島地下ダム|鹿屋シラス分水路トンネル|早咲大橋|志布志国家石油備蓄基地
連絡先:iwamatsu@sci.kagoshima-u.ac.jp
更新日:1997年11月27日