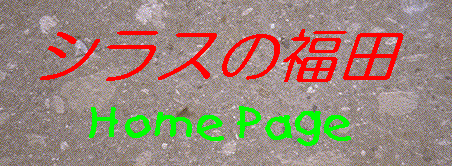
ようこそ|修論発表会講演要旨|'96夏休み成果報告|'95夏休み成果報告|学会発表
先生方に「廊下のドン」と言われています。
[修論発表会講演要旨]
シラス斜面における降雨の浸透形態に関する研究
福田 徹也 (応用地質講座)
Research on Infiltration of Rainwater into Steep Slope of Shirasu
Tetsuya FUKUDA (Chair of Applied Geology)
シラス台地周辺の急斜面では斜面崩壊が多発し,時として人的・公的被害を生じる.シラス斜面崩壊の誘因は豪雨,地震による振動,人工改変などが挙げられるが,これらの中で最も頻繁に発生しているのは降雨を誘因とするものである.そこで本研究では降雨を誘因としたシラス斜面崩壊に焦点を当て,特に降雨水の浸透形態からその発生機構の解明を試みた.さらに本研究で得られた成果から,斜面崩壊の時(降雨状況)の予知・予測への言及を行った.
調査対象地域としたのは鹿児島県のほぼ中央に位置する十三塚原台地(図-1)である.このうち西光寺川の谷頭付近が今回の対象地域である.シラス内の降雨水の浸透形態を把握するには比抵抗の連続測定が有効とされている.そこで今回,斜面上で比抵抗の連続測定を行い,斜面内部への降雨水の浸透形態を明らかにすることを試みた.しかしながら,比抵抗測定では斜面を覆う表土内の浸透形態は言及できないため,表土内の浸透形態はpFセンサーを用いた.加えて斜面下端部からの湧水の電気伝導度ならびに水温の測定を行った.
比抵抗は図-2のように電極を斜面上で0.5m間隔,台地上で2m間隔で設置して測定した.測定された見掛け比抵抗はその時間的変化を表すため,その変化で表現している.これは基準値から測定値の変化を示すものであり,次式で求められる.
Cv=(Mv-Sv/Sv)×100
ただし,Cv:見掛け比抵抗値の変化(%),Mv:ある時刻の見掛け比抵抗値の測定値(Ω-m),Sv:見掛け比抵抗値の基準値(Ω-m).
このようにして得られた比抵抗の変化は,図-2のような降雨状況に伴う変化を示す.7月3日(1995年)は,梅雨が明けた直後であり比抵抗の低下領域が斜面内部にまで及んでいることが分かる.一方,11月3日(同年)は,比較的降雨の少ない時期であり,一度低下した比抵抗が回復している様子が分かる.
このような比抵抗の変化と降雨状況は、降雨(日雨量)を実効雨量の形に変換することにより関連づけられることが明らかになった.実効雨量の変換は,以下の定義(小橋,1993)に基づいている.
Dn=an-1r1+an-2r2+・・・・+a1rn-1+rn ……(1)
ただし,Dn:降雨開始から一日刻みn番目の日の実行雨量,rn:n番目の日雨量,a:降雨の効果の逓減係数(0<a≦1).
(1)式は,今降った雨の効果は一日ごとにaの割合で減少し,現在の状態は過去の降雨の効果の総和であることを意味している.いま前日の実行雨量Dn-1がわかっているとき,Dnは次式で求められる.
Dn=aDn-1+rn ……(2)
逓減係数aは降雨の影響が一日でどの程度減少するかを決定するものである.つまり,a=0のときDn=rnで日雨量を意味し,a=1のときDn=r1+r2・・rn-1+rnとなり積算雨量を意味する.
このような実効雨量と比抵抗の変化とは明瞭な負の相関が見られ,両者は曲線で近似できる(図-3).つまり,シラス斜面内の降雨水の浸透形態は日雨量から換算できることが明らかになった.ただし,シラス斜面表層から0.5~1mの深さは,比抵抗の測定誤差が大きいために,この深さ(シラス斜面を覆う表土)での降雨水の浸透形態は言及できない.
シラス斜面を覆う表土内での降雨水の浸透形態を把握するために,pFセンサーを表土内に設置した.その結果,降雨の浸透形態は斜面内のそれとは異なり実効雨量では換算できない.また,表土とシラスとの境界付近には局所的な飽和帯がに形成されており,降雨状況によって飽和帯の拡大・縮小が繰り返されていることが明らかになった.このような飽和帯が縮小する過程にはその水分をシラス内へ排出,または表土内での下方への移動が考えられる.
シラス斜面内部の降雨水の浸透状況は実効雨量の換算により表現できることから'93年豪雨災害時における斜面内部の浸透状況の算出を試みた.その結果,斜面内部の表層では比抵抗の大幅な低下が見られた.このことから斜面内部の表層では湿潤状態に近いものと判断できる.このような浸透状況下では,表土内における水分(飽和帯)のシラス内への排出機能が著しく低下することが予想される.その結果,シラス斜面を覆う表土内での飽和帯が拡大し,表層崩壊が発生すると考えられる.
上述のようなことから,シラス斜面の崩壊発生は,斜面内部の湿潤状態(降雨水の浸透状況)を客観的に判断することにより,降雨を誘因とした崩壊発生の時間的(降雨状況からの)予知・予測が可能になると考えられる.
[1996年夏休み研究成果報告]
比抵抗値の連続測定に基づくシラス斜面内への降雨浸透シミュレーションの開発とその評価
1. はじめに
シラス斜面内への降雨水の浸透形態を明らかにするために、筆者らは比抵抗の連続測定をこれまでに行ってきた1),2)。その結果、斜面内へ浸透する降雨水(比抵抗値の経時変化)は、表層から深くなるにしたがって大きなタイムラグが発生することが明らかになり、さらに、浸透水の挙動は、実効雨量で表現することが可能であることを示唆した3)。このようなことから、より詳細なシラス斜面内での比抵抗値の変化と雨量データとの対応をみることによって、浸透水の挙動を雨量データからのシミュレーションが可能であると考えられる。本報告では、これらの解析手法ならびに現段階までに得られた結果を述べる。
2.解析のフローチャートおよびその結果
'95年6月から同年11月までの比抵抗値の経時変化ならびに雨量データに基づき両者の対応関係を調べた。ただし、比抵抗値の経時変化は斜面表層から見かけ上の深さ10mまでの測定数1482点のデータを解析した(下図にフローチャートを示す)。その結果、90%以上の測定点のデータが雨量(実効雨量)と良い相関をもつことがわかり、さらにその80%以上が相関係数0.85以上であることも明らかになった。
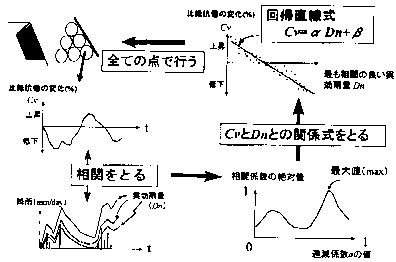
参考文献
1) 福田徹也、横田修一郎、岩松 暉、和田卓也、正木英和(1995):自動電気探査によるシラス斜面での降雨の浸透実態、日本応用地質学会九州支部第11回研究発表予稿集、pp.33-38.
2) 福田徹也、横田修一郎、岩松 暉、和田卓也、正木英和(1996):降雨によるシラス斜面での比抵抗値の時間変化、日本地質学会第103年学術大会講演要旨.
3) 福田徹也、横田修一郎、岩松 暉、和田卓也、正木英和(1996):シラス急斜面での比抵抗値の連続測定(その2)日本応用地質学会平成8年度研究発表講演論文集.
[1995年夏休み研究成果報告]
電気探査2号機の設置
特別研究B(卒論)では,シラスの二次的堆積物の浸食・流出を対象とし研究を進めてきた。しかし,シラス斜面でもっとも頻繁に発生するのはシラス本体の表層崩壊であろう。この種の表層崩壊は個々の規模は小さいが,南九州ではシラスが広大な面積を占めるため,多大な被害になるためである。このような考えに基づき,修士課程における研究ではシラス斜面の表層崩壊に対象を広げ研究するつもりである。
シラスの表層崩壊では,一般的に崩壊の発生は最大時間雨量から崩壊まで数時間のタイムラグが存在するといわれている。このタイムラグの生ずる機構を解明するにはシラス斜面内部への降雨の浸透形態の把握は不可欠である。さらに,これには電気探査(比抵抗の連続測定)を用いるのが最も効果的であると考えられる。
シラス台地の比抵抗変化についてはすでに、当大学と㈱ダイヤコンサルタントとの共同研究が行われた。それに引き続き,当大学と建設技術研究所でシラス斜面の研究が平成6年度より実施中である。このため,修士課程の研究の一環として今年の夏期はこのプロジェクトに参加し電気探査の観測・解析を行った。
 自動電探メンテナンス中のわたし
自動電探メンテナンス中のわたし
平成6年度からの電気探査の観測は,十三塚原台地を開析する河谷の谷壁斜面で行われている(図1)。このデータについてはある程度まとめ上げた。
詳細は11月の応用地質学会九州支部にて発表予定である。
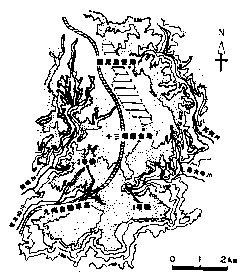 自動電探機設置場所
自動電探機設置場所
ところで,この結果解明すべきいくつかの課題も明らかになってきた、例えば地下水の挙動がそうである。そこで今回,既存の観測機器(1号機)とは別に、新たな観測機器(2号機)を設置することにした(図1)。2号機の設置の目的として,以下のようなものがある。
(1) シラス斜面内部への降雨の浸透形態の解明
(2) 豪雨時におけるシラス内部での地下水面の挙動
(3) 1号機との降雨の浸透に関する比較検討などがある。
現在2号機は正常に作動しているが,8月の大半は落雷によるコンピューターの停止状態が長く続きデータが取れない日が多かった。現段階では地下水の挙動や1号機との比較検討などを述べられる段階ではないが,今後データ数を増やし,2号機のデータを正しく評価していくことが重要な課題である。
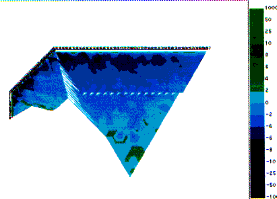 見掛け比抵抗変化率疑似断面図
見掛け比抵抗変化率疑似断面図
1995年7月23日15時を基準としたときの7月27日12時の比抵抗値の変化率を%で表示したもの。暗色方向へ変化するほど、基準日よりも湿ってきていることを示す。
- 福田徹也・横田修一郎・岩松 暉(1995): 豪雨時に多量の土砂流出をもたらすシラスの2次的堆積物.日本地質学会第102年学術大会講演要旨,p.320.
- 福田徹也・横田修一郎・岩松 暉・和田卓也・正木英和(1995): 自動電気探査によるシラス斜面での降雨の浸透実態. 日本応用地質学会九州支部第11回研究発表会予稿集, pp.33-38.
- 福田徹也・岩松 暉・横田修一郎・和田卓也・正木英和(1996): 降雨によるシラス斜面での比抵抗値の時間変化. 日本地質学会第103年学術大会講演要旨, p.350
- YOKOTA,S., FUKUDA,T., IWAMATSU,A., UDA,S., WADA,T. & MASAKI, H.(1996): Infiltration of rainwater from the slope of pyroclastic flow deposits obtained by automatic electric prospecting. Abstracts of 30th IGC, vol.3, p.351.
- 和田卓也・正木英和・西柳良平・岩松 暉・福田徹也(1996): シラス急斜面での比抵抗値の連続測定(その1)―連続測定手法と機器の設置―. 日本応用地質学会平成8年度研究発表会講演論文集, 237-240.
- 福田徹也・岩松 暉・横田修一郎・和田卓也・正木英和(1996): シラス急斜面での比抵抗値の連続測定(その2)―降雨強度と比抵抗値の変化―. 日本応用地質学会平成8年度研究発表会講演論文集, 241-244.
- 福田徹也・岩松 暉・横田修一郎・和田卓也・正木英和(1996): シラス急斜面での見掛け比抵抗値の経時変化と降雨との関連について. 日本応用地質学会九州支部第12回研究発表会予稿集, 20-25.
このページ先頭|ようこそ|修論発表会講演要旨|'96夏休み成果報告|'95夏休み成果報告|学会発表|学生のページ
◎鹿大応用地質学講座もくじ
連絡先:gse-tetu@sci.kagoshima-u.ac.jp
更新日:1997年2月22日
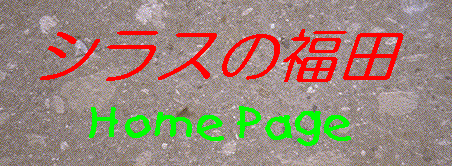
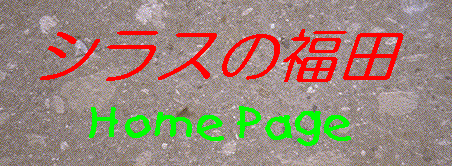
 福田徹也ホームページへようこそ
福田徹也ホームページへようこそ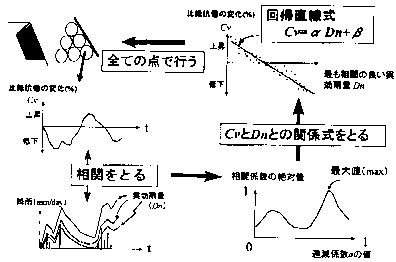
 自動電探メンテナンス中のわたし
自動電探メンテナンス中のわたし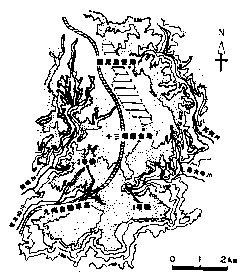 自動電探機設置場所
自動電探機設置場所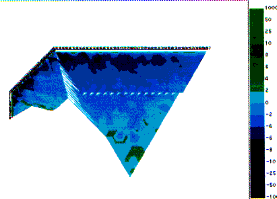 見掛け比抵抗変化率疑似断面図
見掛け比抵抗変化率疑似断面図