なお、「かだいおうち」は日本における大学研究室ホームページの第1号です。歴史的遺産としてここにアーカイブしておきます。
 地震災害と地盤
地震災害と地盤
震災の帯|液状化災害|田町は危ない?|地震保険|地割れと断層|サイスミックマイクロゾーニング
 阪神大震災における震災の帯
阪神大震災における震災の帯
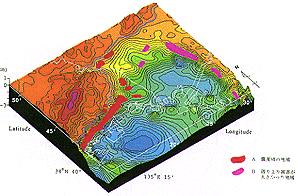 1995年の阪神大震災では、震度7の帯が既存の活断層に平行に出現しました。いわゆる「震災の帯」です。当初、この真下に伏在活断層があるとする説とフォーカシング現象など地盤の影響によるとの説が対立しましたが、結局、地盤説に軍配が上がったようです。図は第四紀層を剥ぎ取った時の基盤の地形を表しています(日本応用地質学会,1998)。基盤地形が急傾斜しているところの近傍に震度の大きいところが集中していることがわかります。
1995年の阪神大震災では、震度7の帯が既存の活断層に平行に出現しました。いわゆる「震災の帯」です。当初、この真下に伏在活断層があるとする説とフォーカシング現象など地盤の影響によるとの説が対立しましたが、結局、地盤説に軍配が上がったようです。図は第四紀層を剥ぎ取った時の基盤の地形を表しています(日本応用地質学会,1998)。基盤地形が急傾斜しているところの近傍に震度の大きいところが集中していることがわかります。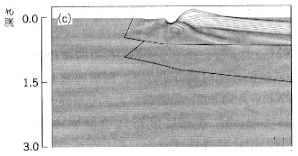 左図は地盤構造を考慮した地震動数値シミュレーションです(入倉,1996)。基盤を通って早く地表に到達した波が二次的表面波に変換され、堆積層を上がってきた実体波と重なり合って大振幅の地震動が形成されたのです。
左図は地盤構造を考慮した地震動数値シミュレーションです(入倉,1996)。基盤を通って早く地表に到達した波が二次的表面波に変換され、堆積層を上がってきた実体波と重なり合って大振幅の地震動が形成されたのです。
 阪神大震災における液状化災害
阪神大震災における液状化災害
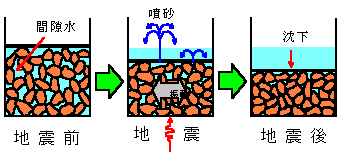 よく締まっていないルーズな砂が地震で揺すられると、砂粒子同士がより締まろうとして隙間の体積が減少します。その結果、水の体積弾性率は大きいので、大きな水圧(過剰間隙水圧)が発生します。そのために、砂粒同士の摩擦力がなくなって、砂粒が水の中に浮いているような状態、つまり液体のような状態になります。これが液状化現象です。
よく締まっていないルーズな砂が地震で揺すられると、砂粒子同士がより締まろうとして隙間の体積が減少します。その結果、水の体積弾性率は大きいので、大きな水圧(過剰間隙水圧)が発生します。そのために、砂粒同士の摩擦力がなくなって、砂粒が水の中に浮いているような状態、つまり液体のような状態になります。これが液状化現象です。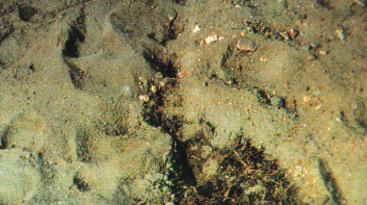 それ故、砂地盤では液状化現象が見られるのは普通です。しかし、阪神大震災では小石程度の礫までが噴出しました(写真:建設技研提供)。いかに地震がすごかったかを物語っています。もっとも礫層までが液状化したのか、液状化した砂に押し出されて出てきたのか検討を要しますが。
それ故、砂地盤では液状化現象が見られるのは普通です。しかし、阪神大震災では小石程度の礫までが噴出しました(写真:建設技研提供)。いかに地震がすごかったかを物語っています。もっとも礫層までが液状化したのか、液状化した砂に押し出されて出てきたのか検討を要しますが。液状化災害は沖積低地や埋立地、さらには谷筋の溜池跡などに集中しました。ほとんどすべて縄文海進時の汀線よりも海側で発生しました。やはり地盤条件が被害状況を左右したのです。
 田町は危ない?
田町は危ない?
 新潟地震では信濃川の旧河道に沿って被害が集中しました。図は新潟市関屋田町周辺の新潟地震地盤災害図です。信濃川が蛇行していた頃の川筋がはっきり読みとれます。ここは昔関屋村といったところで田圃ばかりでした。信濃川沿いの湿地帯だったのです。東京の田町もやはり湿田の跡です。田町という地名のところは地震時には注意しましょう。
新潟地震では信濃川の旧河道に沿って被害が集中しました。図は新潟市関屋田町周辺の新潟地震地盤災害図です。信濃川が蛇行していた頃の川筋がはっきり読みとれます。ここは昔関屋村といったところで田圃ばかりでした。信濃川沿いの湿地帯だったのです。東京の田町もやはり湿田の跡です。田町という地名のところは地震時には注意しましょう。
 地震保険
地震保険
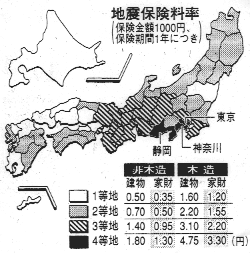 阪神大震災で地震保険がすっかり有名になりました。その保険料率は地震発生確率によって違います。これは阪神大震災が起きる前のデータですが、鹿児島は一番低率の1等地に属しています。つまり、地震に対して一番安全と見なされていることになります。建築基準法でもやはり規制が一番緩やかなところです。桜島が毎日エネルギーを出していてくれるからでしょうか。なお、一番高率の4等地は東海地震が心配されていた東海地域で、兵庫県はこの時も東京と同じく次のランクの3等地に属していました。損保協会は毎年『災害の研究』という本を出すなど、災害研究を熱心に行っていますから、さすがというべきでしょう。
阪神大震災で地震保険がすっかり有名になりました。その保険料率は地震発生確率によって違います。これは阪神大震災が起きる前のデータですが、鹿児島は一番低率の1等地に属しています。つまり、地震に対して一番安全と見なされていることになります。建築基準法でもやはり規制が一番緩やかなところです。桜島が毎日エネルギーを出していてくれるからでしょうか。なお、一番高率の4等地は東海地震が心配されていた東海地域で、兵庫県はこの時も東京と同じく次のランクの3等地に属していました。損保協会は毎年『災害の研究』という本を出すなど、災害研究を熱心に行っていますから、さすがというべきでしょう。
 地割れと断層
地割れと断層
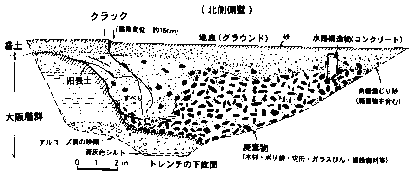 左図は西宮市上ヶ原南小学校校庭で掘られたトレンチの断面です(仲津・横田,1995)。垂直変位約15cm、右横ずれ変位約30cmが認められました。この事実からだけ見れば、一見地表地震断層のようですが、トレンチを掘ってみたところ、実はゴミ地盤が旧地形に平行にずれただけで、基盤の大阪層群は全く切れていません。エセ地震断層だったのです。
左図は西宮市上ヶ原南小学校校庭で掘られたトレンチの断面です(仲津・横田,1995)。垂直変位約15cm、右横ずれ変位約30cmが認められました。この事実からだけ見れば、一見地表地震断層のようですが、トレンチを掘ってみたところ、実はゴミ地盤が旧地形に平行にずれただけで、基盤の大阪層群は全く切れていません。エセ地震断層だったのです。これをスケールアップして類推してみると、遠地で発生した大地震で第四紀の堆積盆地が揺すぶられて、基盤とは無関係な地割れができることも考えられます。第四紀層を切るものはすべて活断層などとするのは早計です。本当に基盤までずらしているか十分吟味しなければなりません。もちろん、今後動く可能性があるかという点は別に検討が必要です。
 サイスミックマイクロゾーニング
サイスミックマイクロゾーニング
阪神大震災以来、活断層が過度に注目され、活断層が近くに無ければ安心してもよいとの誤解すら生まれています。しかし、遠く離れた海溝で地震が起きても被害は発生するのです。上記のように、震源がどこであろうと、地盤状況が震災被害と密接に関係します。事前に地質調査を実施して、表層地盤の状態を把握しておくことが重要です。地盤の地震応答を考慮した詳細なマップが求められています。サイスミックマイクロゾーニングと言います。いわばそれぞれの地域の震災の帯を事前に見つけておくのです。地震予知も大切ですが、それだけが震災対策のすべてではありません。マイクロゾーニングによる被害の空間的予測がそれ以上に重要です。地盤が弱く大被害が予想されるところを洗い出し、そこに重点的な防災対策を施すことによって、被害の軽減が図られるからです。
ページ先頭|震災の帯|液状化災害|田町は危ない?|地震保険|地割れと断層|サイスミックマイクロゾーニング
地震防災関連サイト
連絡先:iwamatsu@sci.kagoshima-u.ac.jp
更新日:1999年1月19日